電話で
お問い合わせ
0120-554-262
葬儀の知識
忌引休暇は何日とれる?電話やメールでの伝え方や取得方法も解説します
2025/7/11作成
2025/7/11更新

家族や親族がお亡くなりになった際、忌引き休暇は何日取得できるのでしょうか。また、申請方法や、そもそも自分が忌引き休暇の対象なのかわからないという方もいるでしょう。 そこで、今回は、忌引き休暇の取り方や取得時の注意点、「忌引き休暇中に給与は発生するのか?」など、忌引き休暇の基本を解説します。 これから忌引き休暇を取得するご予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
目 次
忌引き休暇とは?
家族や親族など近しい人がお亡くなりになった際に、お通夜や葬儀に参列したり、各種手続きを行なったりするために取得する休暇のことを「忌引き(きびき)休暇」といいます。会社によっては「慶弔休暇」あるいは「服喪休暇」ということもあり、「忌引き」には社会活動を控え、喪に服すための期間という意味が込められています。
忌引き休暇の対象となる親族の範囲
忌引き休暇は、一般的に3親等までの親族が対象となります。3親等というのは、故人を基準として3世代前の祖先(曾祖父母)、3世代後の子孫(ひ孫)、兄弟姉妹の配偶者や叔父、叔母、甥、姪などのことを指します。
【3親等以内にあたる人とは】
0親等:配偶者
1親等 :父母・配偶者の父母・子・子の配偶者
2親等 :祖父母・配偶者の祖父母・孫・孫の配偶者・兄妹姉妹・兄弟姉妹の配偶者
3親等 :曾祖父母・配偶者の曾祖父母・ひ孫・ひ孫の配偶者・叔父叔母・叔父叔母の配偶者・甥・姪・甥姪の配偶者
忌引き休暇の日数は故人との関係性による
忌引き休暇として取得できる休暇の日数は、故人との関係性によって異なります。
忌引き休暇は、法律ではなく会社ごとの就業規則(学生なら生徒手帳)で定められているため、一概に何日ということはお伝えできませんが、たとえば配偶者やお子さんなら1週間〜10日前後、ひ孫なら1日のみなど、故人との関係性が近いほど休暇の日数も多く設定されていることが一般的です。
また、会社や学校によっては甥や姪、叔父や叔母は忌引き休暇の対象とならないこともあるので注意しましょう。
さらに、「遠方での葬儀の場合に追加の休暇が認められるか」、「土日が忌引き休暇に含まれるか」などの細かい条件も、各会社・学校ごとに異なりますので、詳しくは就業規則や生徒手帳を確認しましょう。
ここには、一般的な忌引き休暇の日数を掲載しておきますので、目安として参考にしてください。
【一般的な忌引き休暇の日数】
配偶者 :1週間〜10日
父 母:1週間〜10日
祖父母:3日〜5日
子 :1週間〜10日
兄妹姉妹:3日〜5日
叔父・叔母・姪・甥・曾祖父母・孫・ひ孫:1日
忌引き休暇中に給与は発生する?
忌引き休暇中は有給扱いという会社もあれば、無給になってしまう会社もあります。こちらも会社によって異なりますので、就業規則を確認しましょう。ちなみに、無給になってしまう場合、有給休暇を消化する形で休暇を取得するという方もいらっしゃいます。
忌引き休暇の申請方法
忌引き休暇を申請する際の手順は以下のとおりです。
【 忌引き休暇取得までの一般的な手順】
1. 就業規則(または生徒手帳)を確認する
2. 直属の上司に電話や対面で連絡をする
3. 内容確認のメールを送る
上記の通り、まずは、就業規則や生徒手帳で、取得日数や条件を確認します。
次に、直属の上司に忌引き休暇の連絡をしましょう。連絡方法は、電話または口頭が基本です。連絡をうけた上司は欠員を埋めたり、仕事の計画を調整したりする必要があるため、なるべく早めに連絡をするのがマナーです。
伝える内容は
「休暇の取得日数」
「期間」
「葬儀に関する内容」
「休暇中の連絡先」
の4点です。
また、電話や口頭で伝えた後、同じ内容をメールに書いてお送りしておくと間違いがなく安心です。
電話連絡が難しい場合は先にメールを入れておく
明け方や深夜などにお亡くなりになった場合などは、すぐに電話をするとかえって失礼にあたってしまいます。その場合は、先にメールを入れておいて、就業時間になったら改めてお電話を入れるという方法を取りましょう。
忌引き証明書が必要な場合がある
会社や学校によっては、忌引き証明書が必要になることがあります。
忌引き証明書とは、葬儀があったことを証明できる書類のことで、「火葬許可証」や「葬儀の案内ハガキのコピー」などがこれに該当します。忌引き証明書が必要かどうかは会社や学校にもよるため、求められた場合は、上述のいずれかの書類を提出しましょう。
ちなみに会社によっては、慶弔見舞金が支給されることがありますが、その際にも忌引き証明書を求められることがあります。
電話・メールで忌引き休暇を申請する際の例文
次に、実際に電話やメールで忌引き休暇を申請する際の例文をお伝えします。
【電話での伝え方】
電話での連絡は、なるべく会社の就業時間内に行いましょう。連絡先は直属の上司です。
【例文】
〇〇です。本日明け方に、父が亡くなりました。誠に恐縮ですが、◯月◯日〜◯月◯日までの◯日間、忌引き休暇をいただきたくご連絡いたしました。
葬儀の詳細につきましては、決まり次第、改めてご連絡させていただきます。
何かありましたら、私の携帯090-□□□□- □□□□までご連絡ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
もし、業務の引き継ぎなどで伝えるべきことがあれば、このタイミングで共有しておくことも大切です。具体的な業務内容や、進捗状況、今後のスケジュールなどを伝えておくとよいでしょう。
【メールでの伝え方】
お亡くなりになったタイミングが深夜早朝だった場合など、すぐに電話連絡をすると失礼にあたってしまう場合には、先にメールでお伝えし、後からフォローの電話を入れましょう。その場合のメールでの例文は以下の通りです。
【例文】
件名:〇〇です。忌引き休暇を申請します。
本文:
〇〇課長
いつもお世話になっております。
〇〇です。朝早くに失礼します。
先ほど父が他界しました。
急な申し出で大変恐縮ですが、◯月◯日〜◯月◯日までの◯日間、忌引き休暇をいただきたくお願い申し上げます。
また改めてお電話させていただきますが、休暇中の連絡先は、
090-□□□□- □□□□です。
なお、葬儀の詳細につきましては、詳細が決まり次第ご連絡いたします。
お忙しい中ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
署名
先に電話で連絡を入れた場合も、忌引き休暇の日数や期間、連絡先を改めてメールで連絡しておくと丁寧です。その際の例文は以下の通りです。
〇〇です。
先ほどお電話にてお伝えした内容を、念のためメールでもご連絡させていただきます。
忌引き休暇取得日:◯月◯日〜◯月◯日までの◯日間
休暇中の連絡先:090-□□□□- □□□□
葬儀の詳細:改めてご連絡いたします。
お忙しい中ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
署名
忌引き休暇を取得する際の注意点
忌引き休暇を取得する際は、忌引き休暇の条件の確認と的確な引き継ぎがポイントになります。
就業規則や生徒手帳を事前に確認しておく
事前に就業規則や生徒手帳で忌引き休暇の日数や条件を確認してから連絡をしましょう。万が一わからない場合は、担当部署または上司に確認をしても構いません。
引き継ぎは明確に
忌引き休暇の間の業務を引き継いでもらう必要がある場合は、進捗と今後のスケジュールを共有した上で、「いつまでに何をしてほしいか」を明確に伝えましょう。
忌明け後のご挨拶も忘れずに
忌引き休暇後に、業務を引き継いでくれた同僚や上司に、葬儀の報告とお礼の気持ちを伝えましょう。また、ご迷惑をかけてしまった取引先などがあれば、そちらへのご挨拶も忘れずに行いましょう。
忌引き休暇はルールを確認し早めの連絡を心がけよう(まとめ)
忌引き休暇は、会社や学校ごとに取得の条件が決められているため、まずは就業規則や生徒手帳をしっかり確認し、自分が対象か、対象であれば何日間取得可能かを確認することが大切です。その上で、直属の上司もしくは担任の先生になるべく早めに連絡をしましょう。
また、葬儀の準備や内容でわからないことがあれば、葬儀社の事前相談を活用するのもおすすめです。
さがみ典礼では、24時間365日、いつでも無料の事前相談を承っています。また、事前相談で、葬儀費用が最大10.5万円引になる割引制度もございます。まずは、ご相談だけでもお気軽にご利用ください。
さがみ典礼の無料の事前相談はこちら
福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください

関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習にそって、ご家族が亡くなった直後から親身になってお手伝いし、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。
今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。
TEL:0120-554-262
今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。
▼24時間365日、無料で電話相談受付中

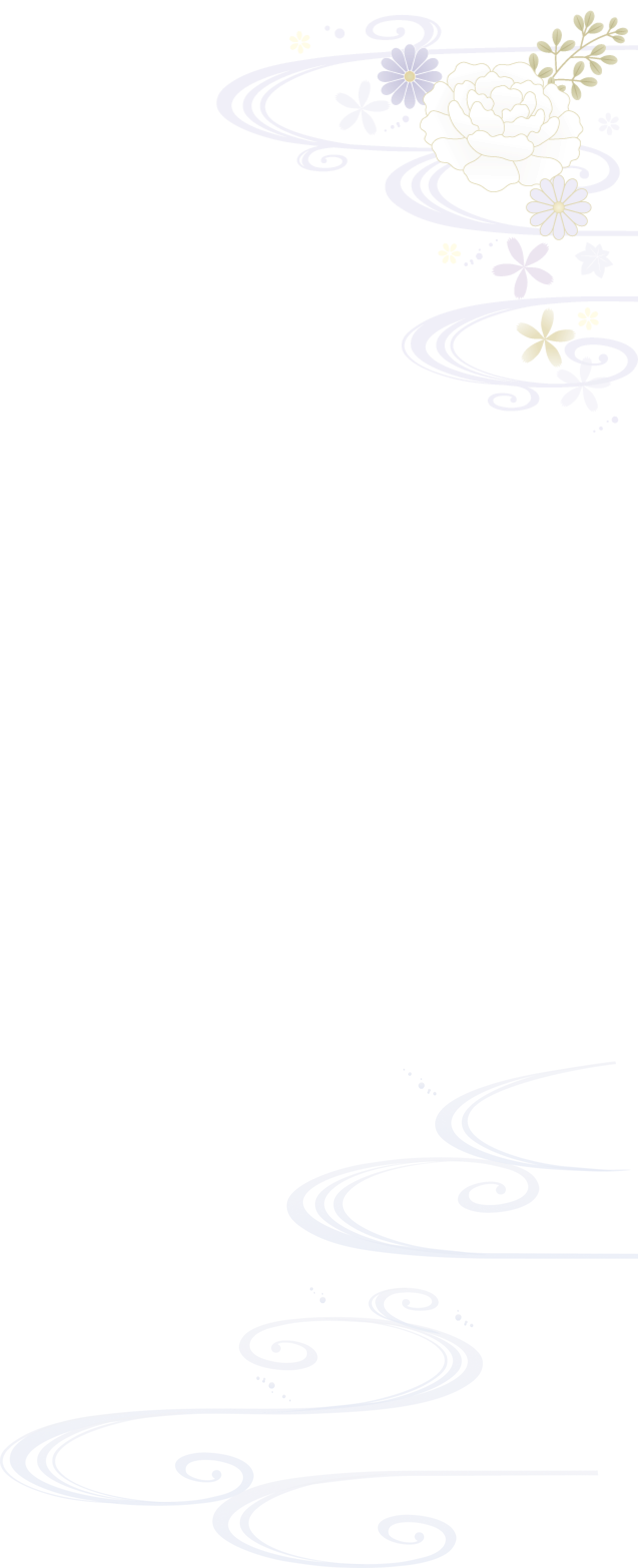
葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください
葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。
電話でお問い合わせ













