電話で
お問い合わせ
0120-554-262
葬儀の知識
【法事の香典マナー】金額の相場や香典袋の書き方・入れ方・渡し方を解説
2025/7/18作成
2025/7/24更新

香典にお包みする金額は、故人との関係性や法要の種類などによっても変わるため、法事に参列する際、いくら包めばよいのかで悩まれる方は多いと思います。香典は多ければ多いほどよいというものでもなく、適切な金額を包むことが大切です。 そこで今回は、法事に持参する香典金額の目安を、故人との関係性や法要別に解説します。 あわせて香典袋の選び方や書き方、お札の入れ方や渡し方のマナーも紹介しますので、これから法事に参列するご予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
目 次
香典とは
香典とは、葬儀や法事の際に、お悔やみの気持ちを込めて贈るお金のことをいいます。
昔は、お金ではなくお香をお供えするのが一般的でしたが、遺族の負担を軽減する相互扶助の考えから、明治時代〜昭和初期頃にかけてお金を渡す慣習が定着したといわれています。
法要の種類
まずは、法要にも種類があることをご説明したいと思います。
法要には、忌日法要と年忌法要の2種類があります。
【忌日法要(きじつほうよう)】
仏教において、故人の逝去後7日ごとに行われる法要のこと。
初七日(しょなのか)・・・ご逝去から7日目に行われる法要
※最近は繰り上げ初七日などといって葬儀当日に初七日法要を行うご遺族も多いです。
二七日(ふたなのか)・・・ご逝去から14日目に行われる法要
三七日(みなのか)・・・ご逝去から21日目に行われる法要
四七日(よなのか)・・・ご逝去から28日目に行われる法要
五七日(ごなのか)・・・ご逝去から35日目に行われる法要
六七日(むなのか)・・・ご逝去から42日目に行われる法要
四十九日(しじゅうくにち)・・・ご逝去から49日目に行われる法要
百カ日(ひゃっかにち)・・・ご逝去から100日目に行われる法要
【年忌法要(ねんきほうよう)】
決められた節目の年の命日に行う法要のこと。
一周忌・・・ご逝去から1年が経った日に行われる法要
三回忌・・・ご逝去から2年後の命日に行われる法要
七回忌・・・ご逝去から6年が経った日に行われる法要
十三回忌・・・ご逝去から12年が経った日に行われる法要
十七回忌・・・ご逝去から16年が経った日に行われる法要
二十三回忌・・・ご逝去から22年が経った日に行われる法要
二十七回忌・・・ご逝去から26年が経った日に行われる法要
三十三回忌・・・ご逝去から32年が経った日に行われる法要
三十七回忌・・・ご逝去から36年が経った日に行われる法要
四十三回忌・・・ご逝去から42年が経った日に行われる法要
四十七回忌・・・ご逝去から46年が経った日に行われる法要
五十回忌・・・ご逝去から49年が経った日に行われる法要
百回忌・・・ご逝去から99年が経った日に行われる法要
※多くの宗派では、三十三回忌または五十回忌をもって弔い上げとしています。
また、これ以外に、ご逝去後初めて迎えるお盆でほ、初盆法要が行われます。
法要と法事の違い
法要は、前述したような忌日法要や年忌法要のことをいい、法要では僧侶による読経や法話が行われます。
一方、法事は、法要後の会食や墓参りなども含めた行事全般のことをいい読経と法話による儀式を指す法要と使い分けられています。
忌日法要は省略されることも多い
上述した法要のうち、現代では、初七日と四十九日以外の忌日法要は省略されることが多くなっています。行なった場合も、基本的に香典は必須ではありません。香典が必要かどうかは地域差もあるため、親族や近所の年長者に確認しておくと安心です。
法事の香典金額の目安
次は、法事に持参する香典金額の目安を法要の種類ごとにお伝えしたいと思います。
初七日の香典
初七日法要は、葬儀当日に執り行われる場合と、別日程で執り行われる場合があります。特に都市部では、葬儀当日に繰り上げて行われることが多くなっています。
ちなみに初七日法要は、葬儀当日に行う場合も、別日程で行う場合も、基本的に親族など身近な人のみで執り行われることが一般的です。そのため、あなたがご遺族やご親族であれば、香典を用意しましょう。もしあなたが友人や知人で、遺族から参列依頼がなかった場合には、初七日の香典は不要となります。
・親の場合:1万円~10万円程度
・兄弟の場合:1万円~5万円程度
・祖父母の場合:5千円〜3万円程度
・その他の親族の場合:5千円~3万円程度
・友人・知人の場合:3千円~1万円程度
別日程で行われる場合で、会食が伴う場合は、上記の金額に5千円〜1万円を上乗せしてお包みすることが一般的です。
しかし、初七日法要を葬儀当日に執り行う場合の香典の考え方はさまざまで、葬儀の香典が初七日の香典を兼ねるとするケースや、葬儀には香典を用意し、初七日にはお供物を用意するというケースもあります。
どのような対応をすべきか迷った時には、親族や近所の年長者に確認しておくと安心です。
四十九日の香典
四十九日は、故人のあの世での行き先が決まる大事な日であると同時に、ご遺族が喪に服す期間を終え、日常生活に戻る「忌明け」を迎える日でもあります。
四十九日の香典は、以下の金額を目安にお包みしましょう。
・親の場合:1万円~5万円程度
・兄弟の場合:1万円~5万円程度
・祖父母の場合:5千円〜3万円程度
・その他の親族の場合:5千円~3万円程度
・友人・知人の場合:3千円~1万円程度
また、法要後に会食がある場合は、上記の金額に5千円〜1万円を上乗せしてお包みします。
一周忌・三回忌の香典
年忌法要の中でも、一周期や三回忌といった早い時期の法要では、比較的高めの金額をお包みするのが一般的です。
・親の場合:1万円~5万円程度
・兄弟の場合:1万円~5万円程度
・祖父母の場合:5千円〜3万円程度
・その他の親族の場合:5千円~1万円程度
・友人・知人の場合:3千円~1万円程度
また、法要後に会食がある場合は、上記の金額に5千円〜1万円を上乗せしてお包みしましょう。
七回忌以降の香典
七回忌以降は親族のみで執り行われることが多いです。
香典額は、一周忌や三回忌の半額〜7割程度の金額を目安にお包みしましょう。また、法要後に会食がある場合は、5千円〜1万円を上乗せしてお包みします。
法事の香典で注意すること
香典金額は、一般的に3千円、5千円、1万円、3万円、5万円、10万円のいずれかとなることが多いです。「4」や「9」がつく金額は、死や苦しみを連想させるため避けるのがマナーです。
夫婦で参列する場合は、2名分の金額をまとめて一緒の香典袋にお包みします。会食がある場合は2人分の会食費用も考慮してお包みしましょう。
諸説ありますが、香典に入れるお札は、新札よりも使用感のあるお札が好ましいとされています。新札しかない場合は、少し折り目をつけるなどしておくとよいでしょう。
香典袋の選び方・書き方・お札の入れ方のマナー
包む金額が決まったら、次は香典袋を用意します。香典袋はコンビニや100円ショップなどで手軽に購入することができますが、宗派や宗教、お包みする金額にみあったものを選ぶようにしましょう。
香典袋の選び方
水引の種類:結び切り または あわじ結び
水引の色:黒白 または 双銀 ※地域によっては黄色と白も可
【金額別 香典袋の選び方】
3千円〜5千円・・・水引がプリントされた香典袋
1万円〜3万円・・・黒白の水引がついた水引金封
〜5万円・・・双銀のあわじ結びの水引が付いた中金封
10万円〜・・・双銀のあわじ結びの水引が付いた大金封
香典袋の書き方
香典袋には表書きと氏名などを記載します。墨の色は、四十九日前の法要であれば薄墨、四十九日以降は通常の濃い墨で書きましょう。
香典袋に書く表書きは「御香典」「御霊前」「御仏前」などが一般的です。ただし「御霊前」と「御仏前」は、法要によって使い分けられているので注意が必要です。
「御霊前」・・・葬儀や四十九日を迎える前までの法要
「御仏前」・・・四十九日以降の法要
ちなみに、亡くなった方はすぐに仏になられるという考えの浄土真宗では、葬儀や四十九日を迎える前にも「御仏前」を用います。浄土真宗の法要に参列する際は注意しましょう。
また、表書きの下には氏名をフルネームで記載します。表書きよりも一回り小さめの文字で書くようにしましょう。
さらに、香典袋にはお札を入れる中袋がセットになっていることが多いです。
中袋の表面には金額を記載し、裏面に氏名と住所を記載します。金額は改ざんを防ぐため大字を用いるのがマナーです。
たとえば5万円を包む場合は「金 伍萬圓」となります。
【大字の例】
壱(いち)・弐(に)・参(さん)・伍(ご)・捨(じゅう)・仟(せん)・萬(まん)・圓(えん)
お札の入れ方
お札は、複数ある場合は向きを揃えて入れましょう。
また封筒にお札を入れる向きは、肖像画が書かれている面が下にくるように入れるのがマナーです。肖像画を伏せるのは、故人への弔意や悲しみを表すためといわれています。
香典の渡し方のマナー
法事での香典は、受付があれば受付に、なければ施主に挨拶をするタイミングで直接お渡しします。法要が始まる前に施主にお声がけをしてお渡ししましょう。
【香典の渡し方】
1. 袱紗から香典を取り出す
2. 香典を袱紗の上にのせる
3. 相手にとって正面になる向きにして両手で手渡す
渡す際は、「本日はお招きいただきありがとうございます」「御仏前にお供えください」などひとこと添えてお渡するのがマナーです。葬儀の際に用いる「ご愁傷様です」という言葉は法事では用いないので注意しましょう。
香典はマナーを守ってお渡ししよう(まとめ)
香典は、お包みする金額が少なすぎても多すぎても失礼にあたってしまいます。ご自身と故人との関係性や法要の種類に合わせて、適切な金額をお包みするようにしましょう。
また、香典袋の書き方や渡し方にもマナーがあるため、これから法事に参列するご予定のある方は、事前に正式なマナーを把握しておくことが大切です。
福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください

関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。
今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。
TEL:0120-554-262
今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。
▼24時間365日、無料で電話相談受付中

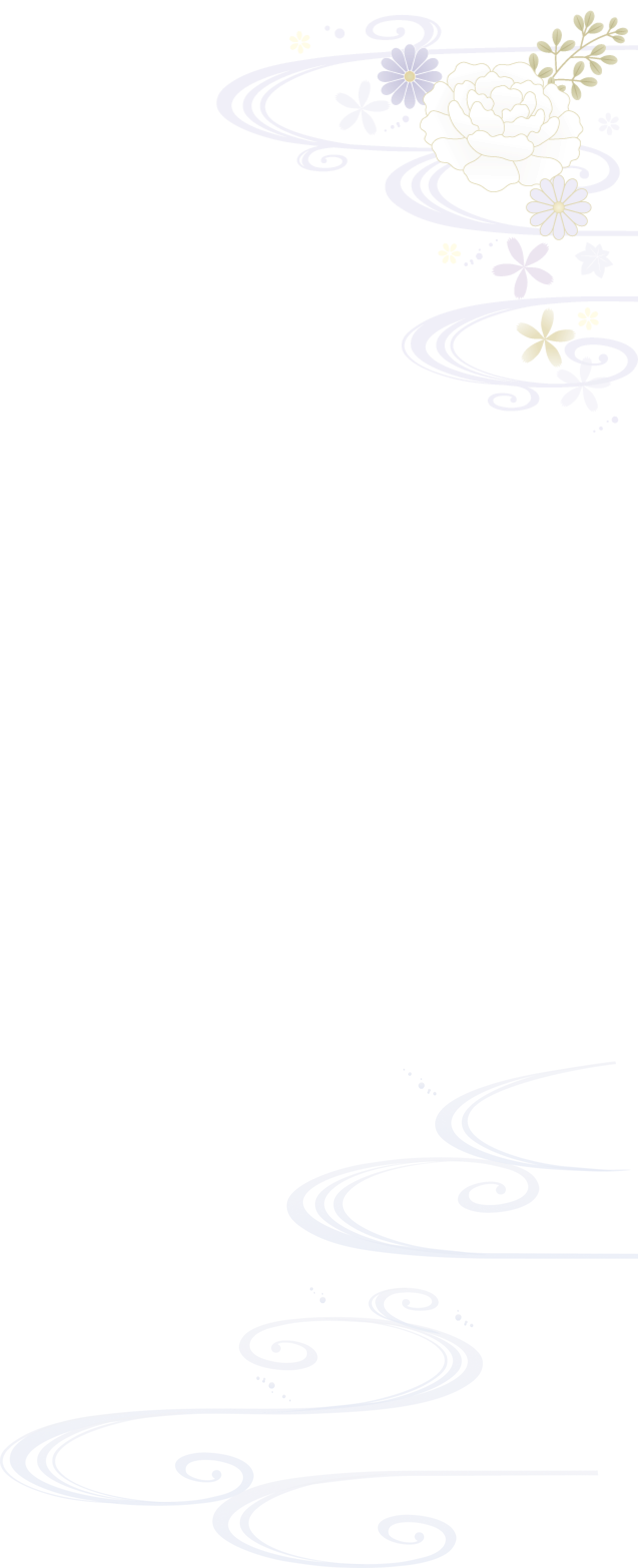
葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください
葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。
電話でお問い合わせ













