電話で
お問い合わせ
0120-554-262
葬儀の知識
【火葬当日の流れ】出棺〜収骨まで。当日の持ち物や火葬のマナーも解説
2025/8/16作成
2025/8/20更新

日本では、亡くなった方は火葬によって弔われることがほとんどです。 しかし、火葬に立ち会えるのは家族や親族など身内のみで、実際に火葬に参列する機会はそう多くはないため、火葬場で何が行われるのか知らないという方もたくさんいらっしゃると思います。 そこで今回は、「火葬当日の流れ」や「火葬場に持っていく持ち物」、「火葬に関するマナーや注意点」について解説します。火葬場での服装マナーや火葬場へ移動する際のルールなどもお伝えしますので、はじめて火葬に立ち会う方や、火葬場での流れや過ごし方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目 次
火葬とは
火葬とは、ご遺体を焼いて弔う葬送方法のことをいいます。
具体的には、ご遺体を焼き、遺骨を拾い、骨壷に収めるまでの一連の儀式を指します。海外では、土葬が主流の国も多いですが、日本では99.9%のご遺体が火葬によって弔われているため、全国各地に火葬場が設置されています。
火葬場に持って行くもの
以下は、火葬場に持参する持ち物の例です。
持ち物については宗旨宗派や地域の慣習によっても異なる場合がありますが、ここでは一般的な仏式の葬儀の場合の持ち物を解説します。
【絶対に必要なもの】
・火葬許可証
・位牌
・遺影
【必要に応じて持参するもの】
・ハンカチ
・数珠
・副葬品
・香典(火葬式・直葬の場合)
火葬許可証
火葬許可証は、ご逝去後、役所に死亡届を提出する際に、一緒に火葬許可申請書を提出することで発行してもらえる書類です。
この手続きは葬儀社が代行してくれるケースも多いですが、ご自身で提出した場合は、火葬当日に忘れずに持参するようにしましょう。
もし火葬許可証を忘れてしまうと、火葬を執り行うことができなくなってしまうため注意が必要です。
位牌
仏教において位牌は、故人の魂が宿る場所と考えられています。そのため火葬場には必ず位牌を持参しましょう。(ただし宗派によっては、位牌を必要としない場合もあります。)
遺影
遺影は、参列者が故人の面影を偲び、生前の姿を思い出すために飾られるものです。火葬場では、火葬炉の前に飾られ、参列者が冥福を祈る際の象徴となります。
ハンカチ
ハンカチは、エチケットとしても普段から持ち歩いている人も多いと思いますが、火葬場では涙を拭くために使用することもあります。
数珠
仏式の葬儀の場合は、数珠を持参することが望ましいとされています。
ただし数珠は、仏教で念仏を唱える際に用いられる道具のため、仏式以外の葬儀や、無宗教の葬儀では不要になります。
副葬品
副葬品とは、故人の棺に入れる品物のことをいいます。
希望があれば、火葬の前に故人の思い出の品や好きだったものなどを一緒に棺に入れることができます。
もし、棺に入れたいものがあれば持参しましょう。
ただし副葬品として適さないものもあるため、事前に火葬場の注意事項を確認しておくとよいでしょう。
香典
お通夜や葬儀を行わない「火葬式・直葬」の場合は、火葬場に香典を持参するケースもあります。「火葬式・直葬」に参列する際、喪主から事前に香典辞退の申し出がなかった場合は香典を持参しましょう。
その際、香典は袱紗に入れて持ち歩くのがマナーです。
火葬当日の流れ
次に、火葬当日の流れについて順を追って解説します。
【火葬当日の流れ】
出棺
↓
火葬場に到着
↓
納めの式
↓
火葬
↓
収骨
↓
骨壷と埋葬許可証を受け取る
↓
精進落とし
1. 出棺
火葬は、一般的には葬儀・告別式の後に執り行われます。
葬儀会場と火葬場が同じ敷地内にある場合もあれば、車で移動して火葬場へ向かう場合もありますが、いずれの場合も、出棺の儀式の後に棺を霊柩車に乗せて火葬場へと移動することになります。
ちなみに、火葬式・直葬のようにお通夜や葬儀・告別式を省略している場合は、ご遺体を安置している安置場所からの出棺となります。
移動の際は、喪主が位牌、遺族の代表者が遺影をもって霊柩車に同乗し、それ以外の方は、僧侶も含め、葬儀社が用意したタクシーやマイクロバスなどで火葬場まで移動することが一般的です。ただし霊柩車の車種によって同乗できる人数は異なるため、事前に確認の上、誰が同乗するかを決めておくとスムーズです。
2. 火葬場に到着
火葬場に到着後は、受付で火葬許可証を提出します。ただし、火葬許可申請手続きを葬儀社が代行した場合は、火葬場への提出も葬儀社が行うことがほとんどです。
3. 納めの式
火葬場での受付が済んだら、火葬炉の前に棺を置き「納めの式」が行われます。
納めの式では、僧侶による読経や、参列者による焼香が行われます。焼香が終わったら、棺の蓋をあけ、故人との最後のお別れをします。副葬品を持参した場合は、このタイミングで棺に入れましょう。
4. 火葬
最後のお別れをした後、棺が火葬炉へと運ばれ、火葬が執り行われます。
火葬にかかる所要時間は、故人の体格や火葬場の設備によっても異なりますが、1時間前後となっています。
その間参列者は、控え室で待つことになるため、喪主や遺族はお茶やお菓子等で参列者をもてなします。
5. 収骨
火葬場から火葬終了のアナウンスが入ったら、参列者は全員収骨室に集まります。
収骨室では、2人1組になって箸でお骨を拾い骨壷に収めていく収骨(拾骨)の儀式が行われます。この儀式には、「箸」と「橋」をかけて、故人が無事、三途の川を渡れるように「橋渡し」をするという意味が込められています。
この時の箸は、一本が竹製で一本が木製といったように材質が異なる箸を組み合わせた「違え箸」を用いることが一般的です。(地域によっては、長さの違う箸を用いる場合もあります。)
また、収骨のやり方は、2人が同時に同じお骨を拾って一緒に収める方法と、1人が拾ったお骨をもう1人に受け渡して収める方法があり、こちらも地域によって異なりますが、基本的には火葬場のスタッフから案内があるので、それに従って行えば問題はありません。
6. 骨壷と埋葬許可証を受け取る
収骨が終わったら、火葬場のスタッフが骨壷と一緒に埋葬許可証を喪主に手渡します。埋葬許可証とは、最初に提出した火葬許可証に火葬済の押印がされたもので、墓地に遺骨を納骨する際に必要な書類になるため、納骨まで大切に保管しておきましょう。
ちなみに火葬場にもよりますが、埋葬許可証は骨壷とともに桐箱の中に納められていることが多いため、見つからない場合はそちらも確認するようにしましょう。
火葬場での流れはこれで終了です。
なお、この後「精進落とし」を行う場合は精進落としの会場へ、行わない場合は帰路につきますが、その際は、骨壷を喪主が持ち、遺族の代表者2名が位牌と遺影をそれぞれ持って向かうことが一般的です。誰が何を持つかは事前に決めておくとスムーズです。
7. 精進落とし(会食)
精進落としとは、故人の冥福を祈り、僧侶や参列者へ感謝の気持ちを伝えるために設けられる会食の席のことをいいます。
最近は、火葬の待ち時間を利用して精進落としが行われることも多くなっていますが、火葬後に場所を変えて行う場合もあります。
精進落としは、喪主挨拶と献杯の後、故人の思い出話を語り合いながら、集まった方々で食事を楽しみ、最後に再び喪主挨拶によって締めくくられます。
ちなみに、会食の間、遺影・位牌・遺骨は故人のための食事(陰膳)と共に会場の上座に飾られることが一般的です。
また、精進落としの席では喪主や遺族は下座に、僧侶を最上座とし、参列者が上座に座ることが一般的です。
初七日法要について
初七日法要は、本来お亡くなりになった日から数えて七日後に行われる法要ですが、最近は、葬儀・告別式に続けて行われたり、火葬後に再び葬儀会場に戻って行われたりと、葬儀当日に行われることが多くなっています。
ちなみに、前者を「式中初七日」、後者を「戻り初七日(または繰り上げ初七日)」といいます。戻り初七日の場合、火葬終了後に火葬場から斎場へ一旦戻って初七日法要を営んだ後、精進落としの会場に向かうことになります。
火葬場での服装マナー
火葬場での服装は、基本的には喪服です。
多くの場合、葬儀・告別式の会場からそのまま火葬場へ向かうことになるため、喪服で参列することになりますが、火葬のみを行う火葬式・直葬で、喪主から「平服で」などの指定があった場合は、略喪服で参列するのがマナーです。
略喪服とは、男性なら黒または紺・グレーなど落ち着いた色のスーツ、女性なら黒または紺・グレーなど落ち着いた色のワンピースやアンサンブル、スーツなどのことをいいます。
火葬に関する注意点
最後に、火葬や火葬場への移動に関する注意点をお伝えします。
遺族や親族以外に参列してほしい人がいれば前日までに本人に伺う
火葬場まで立ち会うことができるのは、基本的には家族や親族などの身内のみにとなりますが、故人や遺族の意向で身内以外に参列してほしい人がいる場合には、前日までに本人にお伝えし、意向を確認しておきましょう。
移動は誰がどの車で行くか事前に決めておく
火葬当日には、葬儀会場から火葬場、火葬場から精進落としの会場などへの移動が伴います。あらかじめ人数に応じたマイクロバスやタクシーなどを手配しておくことになりますが、誰がどの車に乗るかについても事前に決めておくとスムーズです。
なお、マイクロバスなど移動用車両の予約は、葬儀社が行うことが一般的です。人数や希望を伝え、適切な車両を手配してもらいましょう。
「火葬場への行き帰りは違う道を通る風習」がある
「火葬場への行き帰りには違う道を通る」という風習がありますが、それには「故人の霊が道を覚えて、浄土へ行かずに戻ってきてしまうのを防ぐため」とする説や、行き帰りで同じ道を通ることは「重ねて歩く」ことを意味するため、不幸が重なるとして避けられている説など諸説あります。
ただし、当日の交通事情などにより、同じ道を帰らざるを得ない場合もあるため、もし参列者の中にそのような風習を気にする方がいる場合は、事前に葬儀社に相談しておくことをおすすめします。
相談しておくことで、万が一同じ道を通らざるを得ない場合にも、あえて寄り道をするなどの工夫をしてもらうことができるかもしません。
火葬の流れを知って、いざという時に備えよう(まとめ)
火葬は、故人のお顔を見てお別れができる最後の機会です。実際に何が行われているかは当日になってみないとわからないことも多いですが、事前に流れや注意点を知っておくことで、スムーズな対応ができるようになります。
また、もし火葬についてわからないことがあれば、葬儀社に相談するのもおすすめです。
さがみ典礼では、豊富な知識や経験に裏付けされたスタッフが、お客様のご葬儀へのご不安や疑問に寄り添えるよう、24時間365日無料でご相談を承っております。
まずは、お気軽にご相談ください。
さがみ典礼の無料の事前相談はこちら
福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください
関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。
今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。
TEL:0120-554-262
今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。
▼24時間365日、無料で電話相談受付中

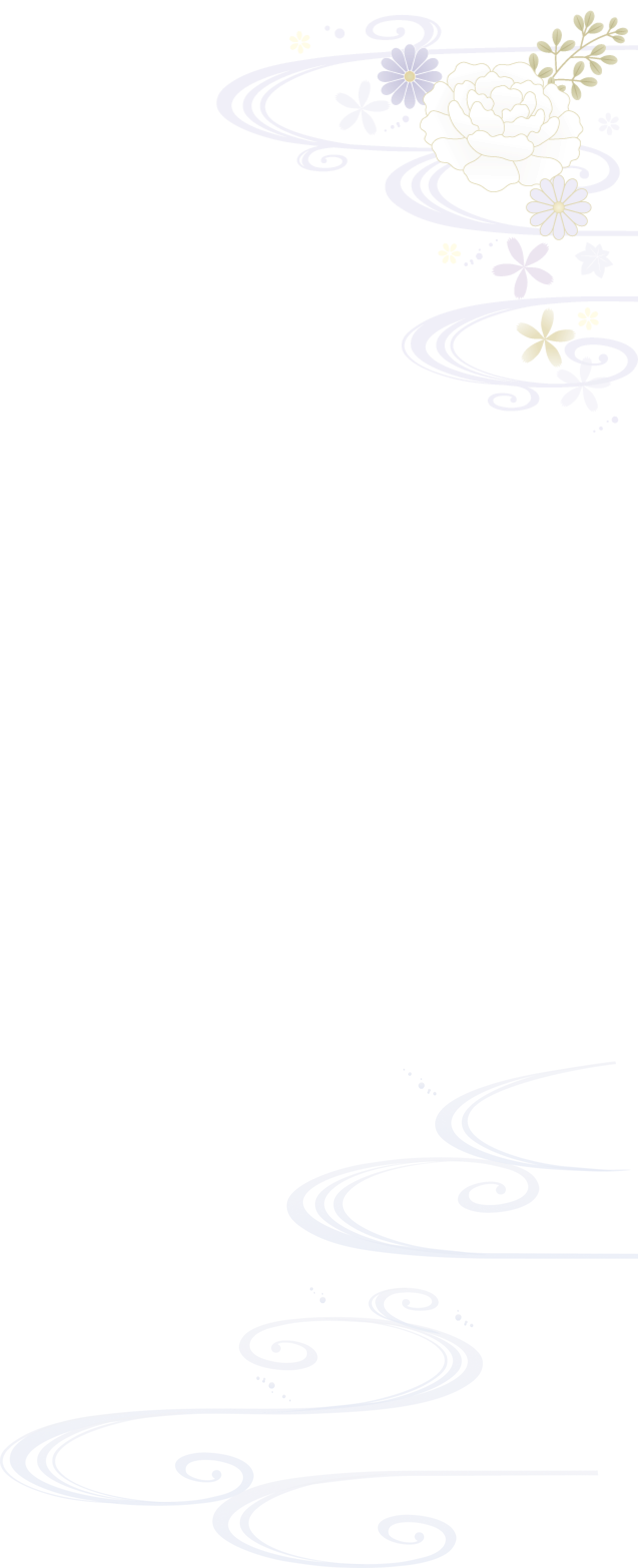
葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください
葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。
電話でお問い合わせ













