電話で
お問い合わせ
0120-554-262
葬儀の知識
葬祭費給付金とは?申請方法と注意点
2025/10/1作成
2025/10/20更新

人生の最期を締めくくる葬儀は、残されたご家族にとっても、集まった人たちと悲しみを共有し、身近な人の死という大きな変化を受け入れるための大切な儀式です。 しかし葬儀には、ある程度まとまった金額が必要になります。その費用を少しでも補助してくれる制度の一つに「葬祭費給付金」があります。 今回は、葬祭費給付金の申請方法や申請時の注意点を解説します。「埋葬料」など葬祭費給付金以外の給付金もご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目 次
葬祭費給付金とは
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったときに支給される給付金のことで、葬儀を行った人(喪主など)が申請をすることで、葬祭にかかる費用の一部が市区町村から助成されます。
なお、申請には期限が設けられており、期限を過ぎると時効となってしまうため、早めの手続きが安心です。
葬祭費給付金の「対象となる人」や「支給金額」「申請期限」は、以下を参考にしてください。
【葬祭費給付金】
|対象者|
亡くなった時点で「国民健康保険」または「後期高齢者医療制度」に加入していた人
|支給対象となる人|
葬儀を行った人(通常は喪主)
|支給金額|
1件につき5万円前後(自治体によって異なる)
|申請期限|
葬儀を行った日から2年以内
葬祭費給付金の申請方法
さっそくですが、葬祭費給付金の申請先、必要書類、申請方法について解説します。
申請先
申請先は、故人の住所地の市区町村役場です。自治体によっても名称は異なりますが「保険年金課」など、国民健康保険や後期高齢者医療保険の担当課が申請窓口になります。
必要書類等
葬祭費の申請には、以下の書類が必要になります。
ただし、自治体によって異なる場合があるため、必ず管轄の自治体のホームページで確認してから申請しましょう。
【必要書類】
・葬祭費支給申請書(役所でもらうか事前にダウンロード)
・故人の保険証(返却している場合は不要)
・葬儀を行ったことがわかる書類(会葬礼状・葬儀の領収書など)
・申請者(喪主)の本人確認書類(運転免許証など)
・振込先口座がわかるもの(通帳など)
・喪主の印鑑(必要に応じて)
※上記のほか、喪主以外の口座に振り込んでもらう場合などには委任状が必要になります。
なお、「葬儀を行ったことがわかる書類」は、会葬礼状でも可能な場合や、申請者(喪主)名義の領収書が必要な場合など、自治体によって条件が異なるため、事前に管轄の自治体の条件を確認しておきましょう。
申請方法
役所の窓口に直接足を運んで申請することができます。ただし、自治体によっては郵送で申請できる場合があるので、郵送対応をしているかどうかは各自治体のホームページで確認しましょう。
葬祭費申請前にやっておくべきこと
故人が国民健康保険に加入していた場合でも後期高齢者医療制度に加入していた場合でも、死後14日以内に健康保険証の返却と「資格喪失届」を提出する必要があります。葬祭費を申請する前に、必ず資格喪失手続きをしておきましょう。
なお、資格喪失届と葬祭費給付金は申請先が同じなので、同時に行うことで手間を省くことができます。
【資格喪失届提出に必要な書類】
・保険証
・資格喪失届(役所でもらうか事前にダウンロード)
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)
葬祭費はいつ振り込まれる?
葬祭費が振り込まれる時期に明確な決まりはありませんが、目安として申請から1~2ヶ月後に振り込まれることが多いとされています。自治体によっても差があるため、もし気になる場合は、申請時に窓口で尋ねてみるとよいでしょう。
火葬式・直葬の場合は受給できない?
葬祭費は、故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されていた場合に支給される給付金ですが、お通夜や告別式などの儀式を行わず直接火葬場でお見送りをする「火葬式・直葬」を行った場合は、受給の対象外となってしまう可能性があります。
自治体によって対応が異なるため、事前に管轄の自治体の条件を確認しておくと安心です。
葬祭費以外の給付金(埋葬料・埋葬費・家族埋葬料・葬祭扶助)
葬祭費以外にも、葬儀や埋葬費用の一部が支給される給付金があります。それぞれ条件や申請方法が異なるため注意しましょう。
埋葬料
故人が会社員や公務員で、勤務先などの健康保険や協会けんぽに加入していた場合は、加入していた健康保険組合または協会けんぽから、故人に生計を維持されていた人(配偶者・子ども・両親)に対して埋葬料が支給されます。
申請者:葬儀を行った人(喪主など)
金額:一律5万円(組合によっては付加給付あり)
申請先:故人が加入していた健康保険組合や協会けんぽ
期限:亡くなった日の翌日から2年以内
埋葬費
埋葬料と同じく故人が会社員や公務員で、勤務先などの健康保険や協会けんぽに加入していた場合に支給される給付金ですが、故人によって生計を維持されていた人がいない場合に、実際に葬儀を行った人(兄弟姉妹など)に支給される給付金です。
申請者:実際に葬儀を行った人
金額:5万円の範囲内で埋葬にかかった実費(健康保険組合によっては付加給付あり)
申請先:故人が加入していた健康保険組合等
期限:埋葬を行った日の翌日から2年以内
家族埋葬料
国民健康保険以外の健康保険に加入している被保険者の扶養家族が亡くなった場合に支給される給付金です。
申請者:組合員本人
金額:一律5万円
申請先:加入している健康保険組合等
期限:葬儀を執り行った日の翌日から2年以内
葬祭扶助
生活保護受給者や生活に困窮しているため葬儀費用を負担できない人に支給される給付金です。親族や施設職員など、実際に葬儀を行う人が事前に市区町村役場の生活保護担当部署に申請することで支給されます。ただし、こちらは現金支給ではなく葬儀社への直接支払いとなることが多いです。また、原則として火葬式・直葬レベルの簡易葬のみが対象となり、必ず葬儀前に申請することが条件となっています。
申請者:実際に葬儀を行う人
支給額:各市区町村が定める実費(目安:上限20万円前後)
申請先:市区町村の福祉事務所(生活保護担当)
申請期限:亡くなった日の翌日から2年以内
葬祭費は、申請方法を確認してスムーズな手続きを(まとめ)
葬祭費給付金は、故人が加入していた公的医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)から支給される葬儀費用の一部補助です。
申請は住所地の市区町村役場の保険担当窓口で行い、申請期限は葬儀を行った日から2年以内です。必要書類や支給額、申請者の条件は自治体ごとに異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください
関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。
今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。
TEL:0120-554-262
今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。
▼24時間365日、無料で電話相談受付中

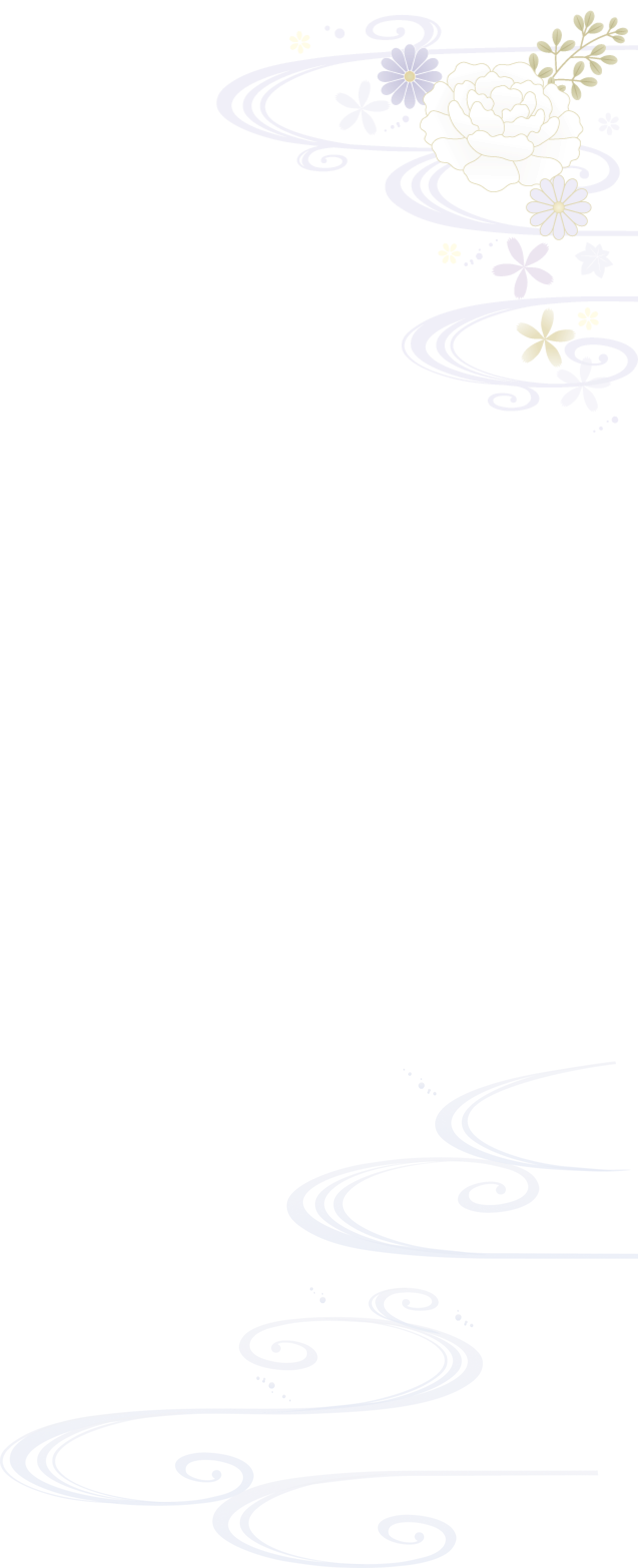
葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください
葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。
電話でお問い合わせ













