電話で
お問い合わせ
0120-554-262
葬儀の知識
家族葬でもお通夜は行う?通夜のマナーと通夜なしの家族葬の注意点
2025/7/22作成
2025/7/24更新

近年家族葬を行う人が増え、一昔前に比べて家族葬に参列経験のある方は増えていますが、それでもいざ、自分が喪主や遺族の立場で家族葬を執り行うとなった時には、従来の葬儀との違いに戸惑いや不安を感じてしまう方も少なくありません。 「家族葬でもお通夜は行うの?」という疑問もそのうちの一つです。 結論を先に申し上げると、家族葬でも基本的にはお通夜を行います。ただし、お通夜を行わないという選択も可能になっています。 そこで今回は、家族葬のお通夜について解説します。家族葬のお通夜を省略する場合の注意点や、お通夜の基本的な流れやマナーもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
目 次
家族葬でも、お通夜は行う?
家族葬では、一般葬と同じように1日目にお通夜、2日目に葬儀・告別式を行うのが基本的な流れになりますが、実は、喪主やご遺族の意向によっては、お通夜を行わないことも可能です。
ちなみに、このようにお通夜を省略し、一日で葬儀・告別式・火葬を行うことを「一日葬」と呼んでいます。
家族葬と一日葬の定義の違い
家族葬は、参列者の範囲を家族や親族など身内に限定して行う葬儀のことをいい、一日葬は、お通夜を省略して1日で行う葬儀のことをいいます。
そのため、家族葬でお通夜を省略する場合は、「家族葬」でもあり「一日葬」でもあるということになります。
お通夜なしの家族葬はある意味自然なこと?
元来、お通夜は一般参列者を迎えず、身内のみが集まって故人との最期のお別れをするための儀式でした。
近年は、お通夜に一般弔問客が参列することも慣例になりつつはありますが、それでも、お通夜は家族や親族など身内のためのものであり、葬儀・告別式は一般会葬者のためのものであるという認識は、今なお残っています。
そのため、身内中心の家族葬の場合、お通夜と葬儀・告別式を必ずしも区別する必要はないとも言えるのです。
家族葬でお通夜を省略するメリット
お通夜を省略することで、通常2日間の葬儀を1日で終えることができるため、ご遺族は参列者対応にかかる心身の負担を軽減することができます。
また、一日だけ参列すればよいという意味では、参列者の体力的負担も軽減できます。特に、遠方から参列するご遺族などは、日帰りで参加しやすくなるため、宿泊費を削減できるなど費用面のメリットも考えられます。
家族葬でお通夜を省略する場合の注意点
家族葬でお通夜を省略する場合は、注意しなければいけないポイントがあるので押さえておきましょう。
事前に、親族からの同意を得ておく
葬儀といえば、お通夜を行うものと思っている人も多いため、伝統を重んじる方や信仰心が強い方の中には、お通夜を省略することに抵抗を感じる方もいるかもしれません。
そのため、お通夜を省略する場合は、独断で決めずに、家族や親族の同意を得た上で行いましょう。
事前に、菩提寺に相談する必要がある
お通夜を省略するということは、宗教儀式を省略することになるので、先祖代々お付き合いをしているお寺(菩提寺)がある場合は、事前に相談をしておく必要があります。
菩提寺によっては、「きちんとした供養ができない」という理由から、お通夜を省略することをよしとしない場合もあります。
もし、菩提寺の許可なくお通夜を省略してしまうと、先祖代々のお墓に納骨できないなどのトラブルに発展してしまう可能性があるため、必ず相談の上で行いましょう。
葬儀後の弔問が増える傾向にある
お通夜なしの家族葬は、参列者の人数を制限し、なおかつ1日しか参列の機会がないため、必然的に葬儀に参列できない人が増えることになります。
そのため、葬儀後、参列できなかった方がご自宅への弔問を希望する機会が多くなり、葬儀後の弔問客対応が増える傾向にあります。お茶やお菓子を用意したり、頻繁に対応に追われたりする可能性があることを念頭に置いておきましょう。
費用が半分になるわけではない
本来2日で行う葬儀を1日で行うため、費用も半分になると思うかもしれませんが、そこまで大きくは変わりません。
通夜を行わない分、飲食費や人件費は削減することができますが、祭壇や棺などにかかる基本的な料金は変わらないため、多少の費用は抑えることができますが、大幅な費用削減は期待しないようにしましょう。
家族葬のお通夜の流れ
続いては、お通夜を行う場合の流れについて解説します。
家族葬のお通夜も、基本的には一般葬と同じ流れで進みます。
ただし参列者が少ない分、焼香に要する時間は少なくて済むため、式全体の時間は短くなる傾向にあります。
【家族葬のお通夜の流れ】
1. 事前準備
2. 受付
3. 開式(読経・焼香)
4. 閉式の挨拶
5. 通夜振る舞い
1. 事前準備
喪主やご家族は、開式の1時間前には会場入りし、事前準備を行います。
会場の設営や準備は葬儀社が行いますので、会場に着いたら動線や返礼品の確認や、供花の並び順の確認などを行なっていただきます。
2. 受付
少人数の家族葬では受付を設けないことも多いですが、受付を設ける場合は、事前に受付係を決めておきましょう。
受付では、芳名帳への記入を促し、参列者から香典を受け取り、返礼品や会葬御礼をお渡しします。
香典を辞退している場合は、事前に受付係に伝えておきましょう。
3. 開式(読経・焼香)
参列者が席に座り、葬儀社から開式の合図があると、僧侶が入場しお通夜がはじまります。
僧侶が読経を行った後に焼香を行いますので、それに続く形で、喪主から順番に参列者が焼香を行います。
すべての人が焼香を終えたら、僧侶が退場し閉式となります。
4. 閉式の挨拶
最後に喪主が閉式の挨拶を行い、通夜が終了します。
挨拶は、参列への感謝を伝えた上で、通夜振る舞いへの参加を呼びかける内容とします。また、翌日の葬儀・告別式の日時と会場名も合わせてお伝えしましょう。
【閉式の喪主挨拶 例文】
本日はご多用の中 父〇〇の通夜に足をお運びいただきまして誠にありがとうございました。
おかげさまで滞りなく通夜を終えることができました。心より感謝申し上げます。
生前親しくさせていただいたみなさまにお集まりいただき、故人もさぞ喜んでいることと思います。
ささやかではございますが、別室にて通夜振る舞いの席を設けさせていただきましたので、お時間の許す限りごゆっくりお寛ぎいただければ幸いです。
なお明日の葬儀・告別式は◯時から〇〇斎場にて執り行います。ご都合のつく方は、ぜひご参列いただければ幸いです。
本日は誠にありがとうございました。
5. 通夜振る舞い
お通夜の後には、参列者や僧侶をもてなし、故人との思い出を語り合う場として通夜振る舞いという会食の席が設けられますが、家族葬では省略されることもあります。
通夜振る舞いを行わない場合は、事前に参列者や僧侶にその旨を伝え、当日は、僧侶には会食の代わりに御膳料を、参列者には粗供養品としてお弁当やカタログギフト、商品券などをお渡しすることが一般的です。
家族葬のお通夜の服装マナー
最後に、家族葬のお通夜に参列する際のマナーをお伝えします。
「平服で」などの案内がない場合は喪服を着用する
家族葬のお通夜に参列する際は、基本的には喪服を着用するのがマナーです。
ただし、事前に「平伏でお越しください」などの案内があった場合は、黒やネイビー、グレーなど地味な色味のスーツやワンピース、アンサンブルなどを着用しましょう。
【喪服とは】
●男性
光沢のない黒無地のスーツ/白いシャツ/黒いネクタイ/黒いソックス/黒い革靴
●女性
光沢のない黒無地のワンピース/アンサンブル/スーツ・黒いシンプルなパンプス(3~5cmのヒールのもの)・30デニール以下の黒いストッキング
基本的に、結婚指輪以外のアクセサリーは外しますが、女性は、パールの一連のネックレスやイヤリングは着用してもよいとされています。二連のものは不幸が重なることを意味してしまうため避けるようにしましょう。
通夜なしの家族葬は親族や菩提寺ともよく話し合って進めよう(まとめ)
家族葬ではお通夜を行うことが一般的ですが、一日葬としてお通夜を省略することも可能です。ただしその場合は、トラブル防止のため親族や菩提寺へ事前に相談して同意を得ておくなどの対応が必要になります。
家族葬でお通夜を行うべきか迷われたときは、葬儀社に相談するのもおすすめです。
さがみ典礼では、豊富な知識や経験に裏付けされたスタッフが、お客様のご葬儀へのご不安や疑問に寄り添えるよう、24時間365日無料でご相談を承っております。
まずは、お気軽にご相談ください。
福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください

関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。
今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。
TEL:0120-554-262
今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。
▼24時間365日、無料で電話相談受付中

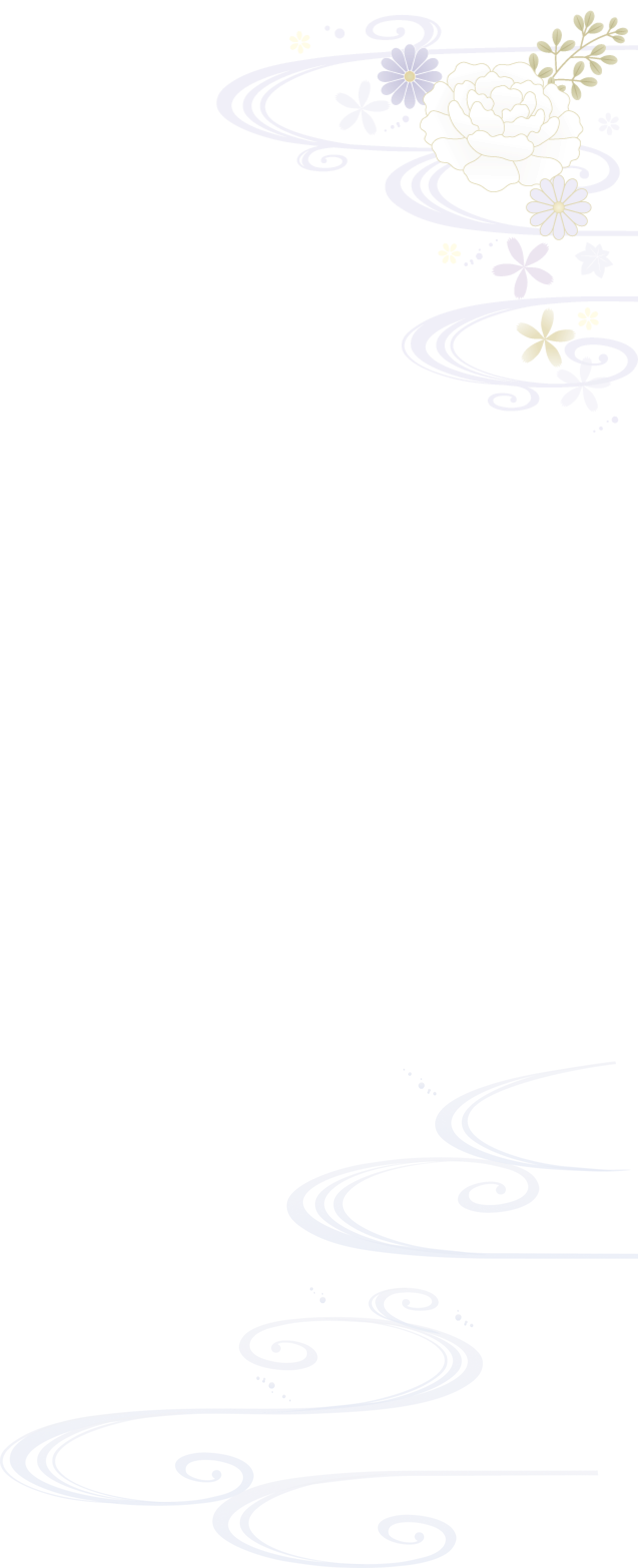
葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください
葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。
電話でお問い合わせ













