電話で
お問い合わせ
0120-554-262
葬儀の知識
家族葬でも香典返しは必要?香典返しのタイミングや相場も解説
2025/8/20作成
2025/8/20更新

一般的に、葬儀や法要で香典を受け取った場合、香典返しをお渡ししますが、家族や親しい方々のみで行う家族葬でも、香典返しは必要なのでしょうか? 家族葬では、香典を辞退するケースも多いです。もちろん、香典をいただかなければ香典返しは不要になりますが、家族葬でも香典をいただいた場合には、香典返しを贈ることがマナーです。 今回は、家族葬で香典が必要なケース・不要なケースについて解説します。香典返しを贈る時期や金額の相場、送り方のマナーもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
目 次
香典返しのタイミング
香典返しを贈るタイミングは、忌明け後1ヶ月以内とされています。仏教に基づく葬儀では、四十九日法要後1ヶ月以内となりますが、四十九日法要が終わってから1週間以内には香典返しを送ったというご遺族が多いようです。
ちなみに、忌明けのタイミングは宗教によっても異なるため、故人の宗旨宗派に応じて、適切なタイミングでお送りしましょう。
【宗教別 忌明けのタイミング】
仏教:四十九日法要後
神道:50日祭後
キリスト教(プロテスタント):「召天記念日」または「記念集会」後
キリスト教(カトリック):「追悼ミサ」後
※キリスト教には「忌明け」や「香典返し」という概念はありませんが、「召天記念日」や「追悼ミサ」のような個人を偲ぶ機会があり、その後に挨拶の品物を贈ることが一般的です。
最近は、当日返しも主流に
最近は、葬儀当日に香典返しをお渡しする当日返し(即日返し)を選ぶご遺族も増えています。
香典返しは、通常いただいた香典金額に応じてお品物を用意しますが、当日返しの場合、あらかじめ全て同じお品物を用意しておき、香典をいただいたその場で香典返しをお渡しするという方法を取ります。
もし高額な香典をいただいた場合には、後日足りない分のお品物をお送りすることになりますが、それ以外の人にはその場で香典返しが完了するため、発送の手間や、金額に応じた品物を準備する手間が省け、お礼の気持ちも直接伝えられるというメリットがあります。
香典返しの金額相場
香典返しは、いただいた香典の半額〜1/3の金額のお品物をお渡しするのがマナーです。このことを「半返し」といっています。
たとえば3,000円の香典をいただいた場合の香典返しは、1,000円〜1,500円程度のお品物をお送りすることになります。
ただし、身内中心の家族葬では、高額な香典をいただくことも少なくありません。そのため、家族葬で高額な香典をいただいた場合は 1/3~1/4程度 のお品物でもよい場合があります。
家族葬でも香典返しが必要なケース
家族葬でも以下のケースは、香典返しが必要です。
四十九日法要を終えた忌明け後1ヶ月以内を目安に、いただいた額の半額〜1/3の金額のお品物をお礼状とともにお送りしましょう。
香典を辞退していなかったため香典を受け取った
家族葬でも、香典辞退の意向がなければ、通常通り香典を受け取ることになります。その場合は、一般葬と同様、香典返しを用意しましょう。
香典を辞退していないのであれば、香典返しを事前に用意し、葬儀当日にお渡しする当日返しを選択することも可能です。当日返しを選ぶことで、葬儀後に香典返しを郵送する手間が省け、ご遺族の負担を軽減することにつながります。
ただし、香典金額にかかわらず同じお品物をお渡しするので、高額な香典をいただいた方には、後日差額分のお品物をお送りすることも忘れないようにしましょう。
香典を辞退していたが、香典を受け取った
家族葬では香典を辞退するケースも多いですが、葬儀に参列いただいた親戚や故人の友人などから、どうしても受け取って欲しいと香典の申し出があった場合は、相手のご厚意に感謝し、ありがたく受け取るのがマナーです。
香典を辞退していたとしても、相手から「香典返しは不要です」という申し出がない場合は、忌明け後にお礼状とともに香典返しをお送りするようにしましょう。
葬儀後に弔問に訪れた人から香典を受け取った
家族葬では、葬儀に参列できる人を限定しているため、参列できなかった方が、後日ご自宅に弔問に訪れる機会が多くなる傾向にあります。
弔問時に、香典を渡したいという申し出があった場合、無理に断らずに、相手のご厚意に感謝しありがたく受け取ることがマナーです。
この場合も、忌明け後にお礼状とともに香典返しをお送りするようにしましょう。
郵送で香典を受け取った
香典辞退の意向の有無にかかわらず、葬儀に参列しない故人や遺族の友人・知人などから、郵送で香典が送られてくる場合があります。
そのような場合、まずは、お礼ともに無事に受け取ったことをお伝えできるとより丁寧です。その上で、忌明け後に、香典返しとお礼状をお送りしましょう。
家族葬で香典返しが不要なケース
以下のケースは、香典返しが不要とされているケースです。
ただし、相手との関係性やいただいた金額などによっては、お返しをした方がよい場合もありますので、臨機応変に対応することが大切です。
香典の代わりにお供え物や供花をいただいた場合
家族葬では香典を辞退しているケースも多いため、どうしても弔意を伝えたいという気持ちから、お供え物や供花をいただく場合があります。
その場合、基本的にはお返しの品は不要とされています。ただし、何もお返しはしないというのは失礼にあたりますので、後日お礼状をお送りして、いただいた供物や供花への感謝をお伝えしましょう。
また、いただいたものが明らかに高額だった場合や相手との関係性によっては、お礼状とともにお品物をお送りした方がよい場合もあります。
お供え物や供花をいただいた場合の対応に、特に決まりはないため、相手に失礼のないよう対応することが大切です。
会社の福利厚生で香典をいただいた場合
会社からの香典で、名義が会社名義だった場合は、福利厚生の一環として導入されている「慶弔金」である可能性が高いため香典返しは不要です。
ただし、会社の方から個人名あるいは連名でいただいた香典の場合は、香典返しが必要です。
四十九日法要を終えた忌明け後1ヶ月以内にお渡しするのがマナーですが、会社の方の場合は、忌引き休暇明けの出社時に、直接手渡しするというケースも多くなっています。
連名でいただいた場合も、個人名が特定できるのであれば、いただいた金額を人数で割った1/3〜半額程度の金額のお品物をそれぞれ個別に用意しますが、個人名が特定できない場合は、小分けになったお菓子などを用意し、代表者にお渡ししても差し支えないとされています。
相手から「香典返し辞退」の意向を伝えられた場合
家族葬では、「香典返しは不要です」と言って香典をお渡しくださる方もいらっしゃいます。その場合は、相手の意向を尊重し、お礼状のみをお送りしましょう。
家族葬の「香典返し」は、何を贈る?
家族葬の香典返しでは、一般的な葬儀と同様、焼き菓子・のり・お茶・コーヒーなどの日持ちする食べ物や飲み物、タオル・ハンカチ・洗剤・石鹸などの日用品などが選ばれています。
これらの品物は食べたり飲んだり、使ったりすることで消えてしまう「消え物」といわれるもので、「不幸を後に残さない」という意味が込められています。
香典返しに添えるお礼状(例文)
香典返しには、お礼状を添えてお送りするのがマナーです。
お礼状には、無事に四十九日法要を迎えたことの報告やお心遣いへの感謝などを綴りましょう。
【お礼状 例文】
亡父◯◯◯儀 葬儀に際しましては ご多用の中にもかかわらずご丁寧な弔意を賜り 誠にありがとうございました おかげさまで滞りなく四十九日の法要を済ませることができました
感謝の気持ちを込めて ここに 心ばかりの品をお送りいたしました
何卒 ご受納くださいませ
本来であれば拝眉の上御礼申し上げるところ 略儀ながら書中をもってご挨拶にかえさせていただきます
令和◯年◯月◯日 ◯◯◯◯名前
お礼状は、縦書きで、句読点はつけずに書くことがマナーです。また、「いろいろ」「ますます」のような重ね言葉や、死や別れを連想させる言葉など、忌み言葉として避けられている言葉もあるため、言葉選びには注意が必要です。
家族葬でも香典を受け取ったら香典返しが必要です(まとめ)
家族葬でも、基本的には香典を受け取ったら、香典返しを贈ることがマナーです。ただし、家族葬の場合は、香典を辞退しているケースも多く、辞退していたのにも関わらず相手から香典の申し出があることもあり、その時々で臨機応変な対応を求められるケースも少なくありません。
家族葬の香典返しで迷われた際には、葬儀社に相談することもおすすめです。
さがみ典礼では、豊富な知識や経験に裏付けされたスタッフが、お客様のご葬儀へのご不安や疑問に寄り添えるよう、24時間365日無料でご相談を承っております。
まずは、お気軽にご相談ください。
さがみ典礼の無料の事前相談はこちら
福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください
関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。
今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。
TEL:0120-554-262
今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。
▼24時間365日、無料で電話相談受付中

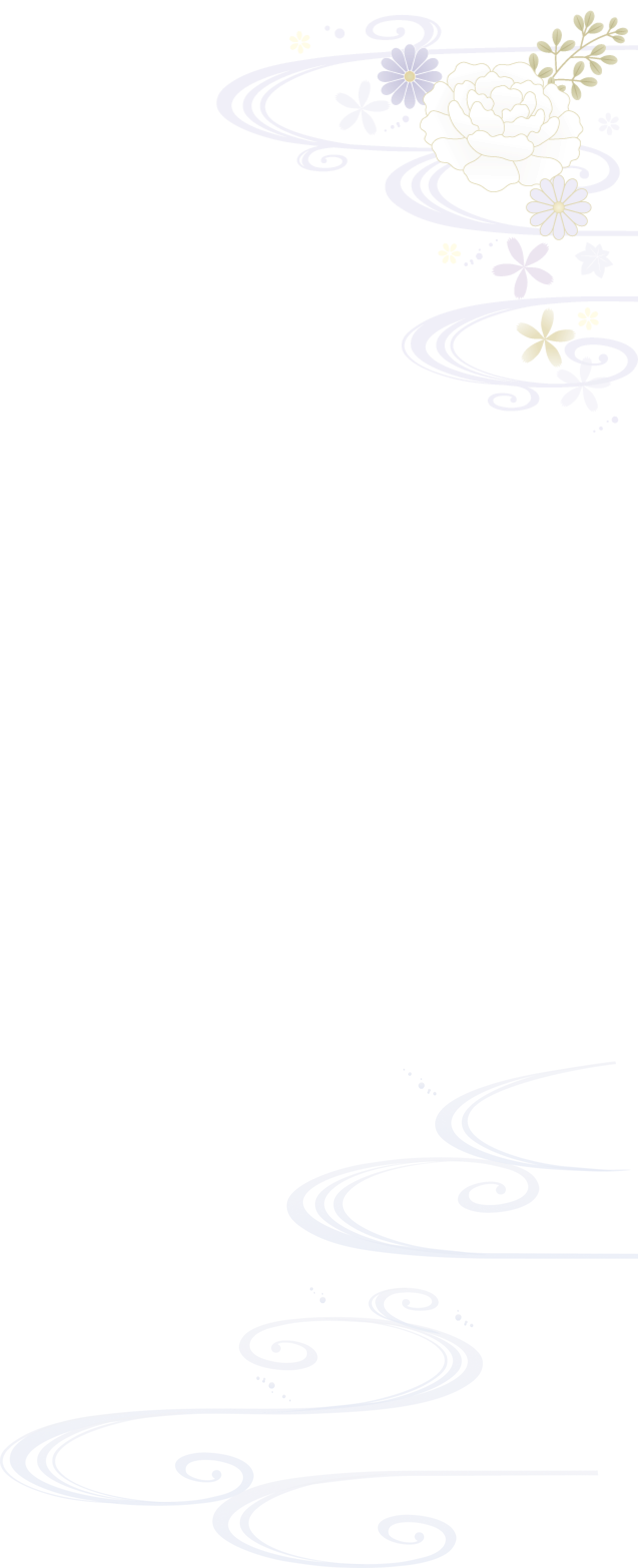
葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください
葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。
電話でお問い合わせ













