電話で
お問い合わせ
0120-554-262
葬儀の知識
火葬場の予約から当日まで、知っておきたい流れと注意点
2025/9/18作成
2025/9/19更新

日本では、ほとんどのご遺体が火葬によって弔われます。そのため、葬儀後は必ず火葬場へ移動し、そこで故人様との最後のお別れをすることになります。 しかし、火葬場はいつ、誰が、どのように予約するのでしょうか。いざ、火葬場の予約が必要になった時に、何から手をつければよいかわからないという人も多いと思います。 そこで今回は、火葬場の予約から当日までの流れを解説します。「葬儀日程の決め方」や「火葬場の予約から当日までの準備で注意すべきポイント」なども解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目 次
火葬場の予約は誰がするの?
ほとんどのケースで、火葬場の予約は葬儀社が行います。個人からの予約を受け付けていない火葬場が多いため、まずは葬儀社に相談してみましょう。
葬儀社なら、登録業者だけが見ることのできるオンライン予約システムを使うことで、深夜や早朝でも火葬場の空き状況を確認することができます。
火葬場を予約するタイミングはいつ?
火葬場や火葬日程は、病院や施設などからご遺体をご希望の安置場所へ安置した後、葬儀社と行う打ち合わせの際に決めることになります。
【火葬場予約までの流れ】
ご逝去
↓
葬儀社に依頼
↓
葬儀社が病院などにお迎えにあがる
↓
ご遺体を搬送する
↓
ご希望の安置場所に安置する
↓
葬儀社との打ち合わせ
↓
火葬場を予約
葬儀日程の決め方
葬儀社との打ち合わせでは、まず火葬場の空き状況を確認し、葬儀当日に読経供養をしていただく僧侶やご遺族のご都合も考慮しながら、葬儀日程を調整していきます。
葬儀形式にもよりますが、一般的には、1日目にお通夜、2日目に葬儀・告別式・火葬を執り行うことになるため、その流れで火葬場が空いていて、ご遺族や僧侶のご都合も問題ないとなってはじめて葬儀日程が確定します。
もし、先に僧侶やご遺族の都合だけで葬儀日程を決めてしまうと、希望日に火葬場が空いておらず再調整が必要になってしまう可能性があるため、必ず、先に火葬場の空き状況を確認し、日程調整を行いましょう。
火葬当日までに必要な準備
次に、火葬当日までにご遺族がするべきことをお伝えします。
火葬許可証の準備
火葬を行うには火葬許可証が必要です。火葬許可証は故人の住民表のある市区町村役場で申請できます。死亡届を提出する際に、一緒に申請することが一般的で、申請するとその場で発行されるので火葬当日まで大切に保管しておきます。
この手続きは、死亡届の提出も含めて葬儀社が代行してくれることも多いので、お願いできるか確認しておきましょう。
安置場所の確保
葬儀当日まで、ご遺体を安全に保管しておける安置場所を確保する必要があります。安置場所はご自宅または葬儀社の安置施設を利用することが一般的です。ご自宅安置の場合、施設利用料はかかりませんが、棺を搬入する際の経路や部屋のスペース、冷房の有無などに条件があるため、安置可能かどうかは事前に確認しておく必要があるので注意が必要です。
火葬場までの移動手段の確認と手配
火葬場が決まったら、参列者や僧侶が葬儀会場から火葬場まで何で移動するかなどを決めておく必要があります。参列者の人数に応じて、マイクロバスやタクシーなどを手配しておきましょう。
この時、僧侶の移動方法も忘れずに確認しましょう。僧侶がご自身で移動するのか、ご遺族が用意した移動手段を使って移動するのかによって、お布施と一緒にお渡しするお車代が必要かどうかが変わってきます。ちなみに、ご自身で移動される場合は、当日、お車代を用意しておきましょう。
精進落とし(会食)の手配
火葬後に精進落としといった会食の場を設けることが多くなっています。会食を行う場合は、レストランまたは仕出し料理などの手配が必要になります。
もし会食を行わない場合でも、会食の代わりに参列者にはお持ち帰り用のお弁当や返礼品をお渡しすることが一般的ですので、その準備が必要になります。
ちなみに、僧侶には食事代の代わりとして「御膳料」をお布施と一緒にお渡しする必要があるため、当日までに用意しておきましょう。
納棺の準備
お通夜の前にご遺体を棺に納める納棺の儀式を行います。納棺は基本的には葬儀社のサポートのもと行われますが、棺の中に入れる副葬品などの希望があれば、事前に準備しておきましょう。
火葬場への持ち物の準備
当日火葬場へ持って行くものは以下の通りです。忘れ物がないように事前に確認しておきましょう。
・火葬許可申請書
→葬儀社が手続きを代行した場合は葬儀社が持参します
・数珠
→仏式の葬儀の場合に必要になります
・ハンカチやティッシュ
→涙をふく際などに必要です
・僧侶へのお布施
→必要に応じてお車代や御膳料も持参します
・位牌や遺影
→位牌は喪主が、遺影はそれ以外の近親者が持つことが多いです
・飲食物
→待合室で過ごす際に必要な場合は持参しましょう
・骨壷や骨箱
→葬儀社が用意してくれることが多いですが念のため確認しましょう
また、お通夜や葬儀を行わず、直接火葬場にてお別れを行う「直葬・火葬式」の場合は、参列者にお渡しする香典返しも火葬場に持参する場合があります。
火葬場が混んでいて予約が取れない場合の対応
都市部などでは、高齢化による死亡者数の増加や火葬場不足などから、火葬場の空きがなく予約がとれない「火葬待ち」となることも少なくありません。場合によっては、ご逝去から葬儀まで1週間〜2週間待たなければいけないケースもあります。
このようにご逝去から火葬までに期間があいてしまう場合、以下のような対応を検討する必要があります。
安置場所を確保する
火葬まで期間があくということは、ご遺体を安置する期間がのびるということでもあります。そのため葬儀日まで利用できる安置場所を確保することが大切です。また、安置期間が延びる分、施設利用料などが予定より多く必要になることも念頭に置いておきましょう。
ドライアイスの追加費用も予算に入れておく
ご遺体を衛生的に保つために、安置場所ではドライアイスを使用することが多いです。特にご自宅で安置する場合はドライアイスが必須となりますが、安置期間が延びれば、必要なドライアイスの量も増えるため、追加費用がかかる可能性があります。
葬儀社のセットプランにはあらかじめドライアイスが含まれていることが多いですが、何日分含まれているかはプランによっても異なりますので、事前にセットプランに何日分のドライアイスが含まれているのかも確認しておくと安心です。
葬儀社に代替えプランを提案してもらう
葬儀社が見ることのできるオンライン予約システムで、他の火葬場に空きがないかも調べてもらい、代替えプランを提案してもらいましょう。もしも、葬儀場からの移動距離が許容範囲内で、すぐに火葬できる火葬場があれば、そちらを検討してもよいでしょう。
ただし、移動距離が増えることで移動にかかる費用がかさんだり、参列者の移動の負担が増えてしまうことも考えられます。また、火葬場の料金は市内と市外では市内の方が安く設定されていることがほとんどなので、費用面の負担が増える可能性があることも念頭に置いた上で検討するようにしましょう。
火葬場の予約から火葬当日までに注意すること
最後に、火葬場の予約から火葬当日までに考慮すべき注意点をお伝えします。
先に火葬場を決めてから葬儀日程を決める
特に、市区町村が運営している公営の火葬場は費用も安く予約が集中しやすいため、希望する日程で火葬場を押さえられないことも多くなっています。
そのため、まず火葬場の空き状況を確認してから、ご遺族や僧侶の都合を調整するようにしましょう。先に葬儀日程を決めてしまってその日に火葬場が空いてないとなると、再度調整しなければならず二度手間になってしまいます。
火葬場までの移動手段を確認しておく
火葬場は駅から離れている場所にあることが多く、公共交通機関を使って行くには難しい場合も多いです。そのため葬儀・告別式後、火葬場への移動は、車などを使うケースが多くなっています。加えて、火葬場の駐車場も限られているため、駐車スペースによっては乗り合わせて向かうなどの対応が必要になる場合もあります。
参列者の中には、ご高齢の方や小さなお子さんがいる場合もあるため、会葬者をまとめて送迎できるマイクロバス等の利用も、必要に応じて検討しましょう。
火葬の予約や準備でわからないことは葬儀社に相談しよう(まとめ)
ご遺族は、大切な方を亡くされた悲しみの中、葬儀や火葬の準備などを行うことになるため、心身ともに大変な時期をお過ごしになられます。
しかも、ほとんどの方が葬儀に不慣れで、右も左もわからない状況の中で、さまざまな決断を下していくことになり、精神的にも肉体的にも負担は大きいでしょう。
そんな時は、ぜひ葬儀社を頼ってください。
さがみ典礼では、豊富な知識や経験に裏付けされたスタッフが、お客様のご葬儀へのご不安や疑問に寄り添えるよう、24時間365日無料でご相談を承っております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
さがみ典礼の無料の事前相談はこちら
福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください
関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。
今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。
TEL:0120-554-262
今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。
▼24時間365日、無料で電話相談受付中

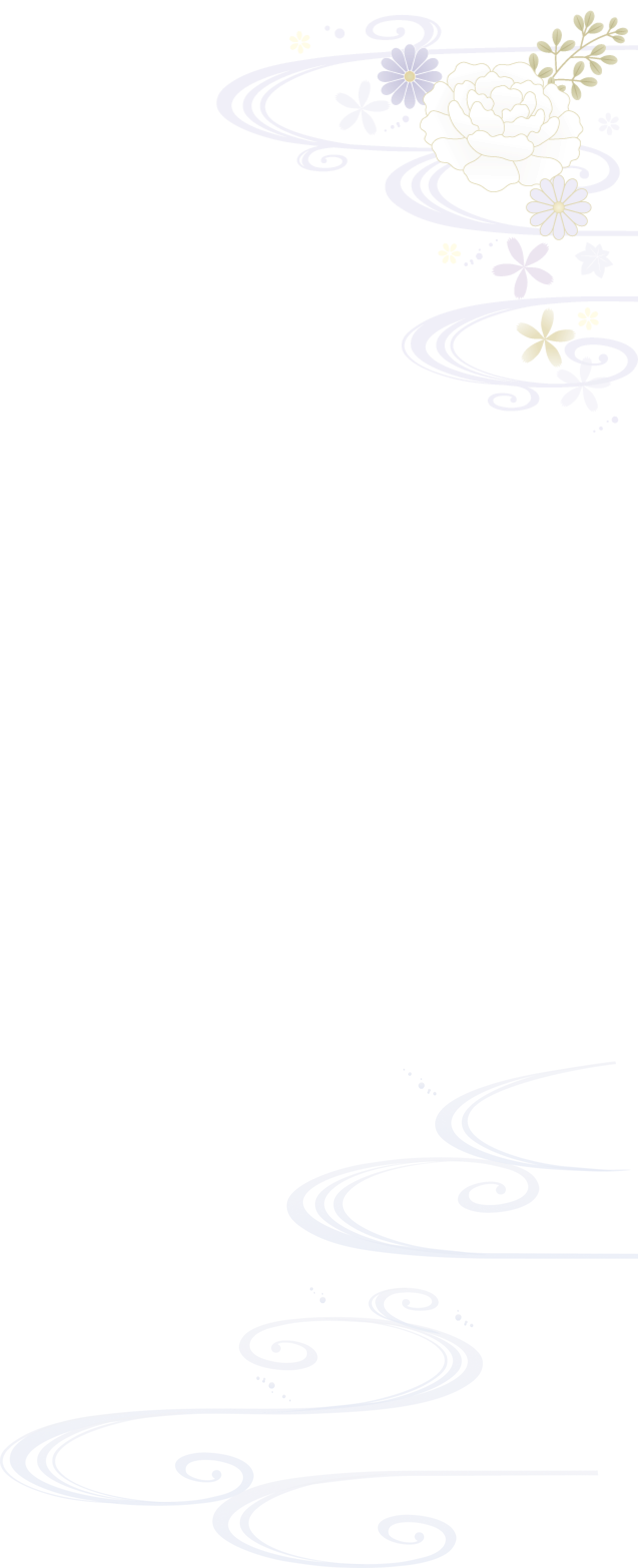
葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください
葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。
電話でお問い合わせ













