電話で
お問い合わせ
0120-554-262
葬儀の知識
自宅葬とはどんなお葬式?費用や流れ、注意点を解説します
2025/7/11作成
2025/7/11更新

葬儀場ではなく、亡くなった方の自宅で行う葬儀を「自宅葬」といいます。住み慣れた我が家で最期のときを迎えられる自宅葬は、長い闘病生活で自宅に帰ることができなかった場合などに、「最期は慣れ親しんだ自宅で見送ってあげたい」というご遺族のお気持ちから選ばれることが多いです。 このコラムでは、自宅葬の流れや、自宅葬を行う前に知っておきたい注意点などをご紹介します。自宅葬のメリットやデメリットにも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
目 次
自宅葬とは
故人の自宅でお通夜や葬儀・告別式を行うことを自宅葬といいます。
現在は、葬儀といえば斎場やセレモニーホールで行うのが一般的になりましたが、今ほど斎場がたくさんなかった一昔前には、多くのご家庭で自宅葬が行われていました。
近年は、核家族化や近所付き合いの希薄化などの社会問題を背景に、特に都市部における自宅葬の件数は大幅に減少傾向にありますが、その一方で、家族葬などの普及によって、アットホームなお葬式の需要が高まっていることから、自宅での葬儀が見直されつつもあります。
自宅葬のメリット
さっそくですが、まずは自宅葬のメリットからお伝えしたいと思います。
住み慣れた家で、最期のお別れができる
故人が自宅が好きな人だったり、長い闘病生活で自宅に帰ることができなかったりした場合に、ご遺族は、「できるだけ長く、故人の愛した自宅で最期の時間を過ごさせてあげたい」と思うのではないでしょうか。自宅葬なら、「最期は自宅で過ごしたい」という故人の願いを叶えてあげることができます。
会場費がかからない
自宅が会場となるため、当然会場費はかかりません。ちなみに葬儀で会場にかかる費用は公営斎場で5~10万円程度、民営斎場で15万円〜40万円程度が相場といわれています。また、それ以外に、葬儀までにご遺体を安置しておく安置施設の費用も必要になります。
自宅葬では、それらにかかる費用の大部分を削減することができます。
自由度の高い葬儀ができる
自宅葬は、会場のルールや時間の制限がないことから、たとえば、故人の好きな食べ物をふるまったり、故人の好きなアロマを焚いたり、部屋を故人の趣味に合わせて飾りつけたりと、より自由度の高い、オリジナリティあふれる葬儀を行うことができます。また、式の時間についても、自宅であれば特に決まりはないため、自由に設定することができます。
近隣住民が参列しやすい
自宅で行う場合、近隣の親族や高齢者などは参列しやすくなります。また、地方などでは、自宅葬を行うと、今も近所の方々による組合が手伝いに来てくれるという慣習が残っているところもあるため、その場合は、人手に困らないという点もメリットの一つです。
自宅葬のデメリット
一方で、自宅葬にはデメリットもあります。
準備や片付けに労力がかかる
一般的な葬儀場なら葬儀用の設備が整っているため、ご遺族が会場の設営などをする必要はありませんが、自宅の場合は、部屋の掃除から会場設営、後片付けまでをご遺族が行うことになり、通常の葬儀よりも労力がかかってしまいます。
プライバシーの問題
自宅葬を行えば、当然、不特定多数の方が自宅に訪れることになるため、プライベートな空間を見られてしまうというリスクがあります。
参列者の人数が限られる可能性がある
自宅葬では、限られた空間で葬儀を行うことになるため、部屋の広さによって、参列者の人数を制限しなければならない可能性があります。
自宅葬で「必ず確認しておくべきこと」とは
自宅は、斎場のように葬儀用に作られた空間ではないため、自宅葬を行う場合は、ご自宅が自宅葬を行える環境かどうかなどを確認しておく必要があります。
まずは、自宅葬ができる環境かを確認する
集合住宅の場合は、マンション等の規約で自宅葬が禁止されていないかを確認しましょう。その上で、エレベーターや玄関など、棺の搬入出経路に充分なスペースがあるかどうかも確認します。
最近は、マンションなどの集合住宅が多くなっていますが、規約で自宅葬が禁止されていることがあるため、必ず事前確認が必要になります。また、エレベーターを使う場合、棺が搬入できるサイズかどうかもチェックポイントになります。玄関や廊下などの搬入経路に棺が通れるスペースが確保されているかどうかも合わせて確認しましょう。
自宅に充分なスペースがあるかを確認する
参列者を招いて葬儀を行うのに充分なスペースがなければ、自宅葬を行うことができません。自宅葬の規模にもよりますが、たとえば小規模な自宅葬の場合、最低でも6畳ほどのスペースが必要といわれています。
近隣へご挨拶をすませておこう
自宅葬を行うということは、不特定多数の人が近所に訪れることになるため、近隣住民への配慮も必要です。自宅葬の日時が決まったら、近所の方へご挨拶に伺いましょう。
ご挨拶の際には、当日、車や人の往来が増えることでご迷惑をおかけしてしまうことなどを伝え、ご了承を得ておくことが大切です。また、葬儀後に、改めて無事に葬儀を終えたご報告とお礼を伝えることも忘れないようにしましょう。
駐車場を確保しておこう
葬儀には、遠方から車で訪れる参列者も少なくありません。路上駐車防止のためにも、近隣の駐車場を借りておくなど、事前に車での来場者の駐車スペースを確保しておく必要があります。
もし駐車場が借りられなければ、ご遺族が車やタクシーで送迎するなどの対応策も検討しておきましょう。
自宅葬の流れ
続いて、自宅葬の流れについてお伝えします。自宅葬といっても、ご逝去から火葬までの流れは一般的な葬儀と同じです。
【自宅葬の流れ】
1.ご逝去
2.葬儀社へ連絡
3.搬送・安置
4.葬儀社との打ち合わせ
5.納棺
6.お通夜
7.通夜振る舞い
8.葬儀・告別式
9.火葬・収骨
10.精進落とし
ご逝去〜葬儀社との打ち合わせ
病院等で医師から死亡診断書を受け取ったら、まず葬儀社に依頼をしましょう。ご遺体の搬送・安置は葬儀社が行いますので、依頼後は葬儀社の到着を待つことになります。
自宅葬の場合、ご自宅を安置場所にするケースが多いかと思いますが、自宅での安置が可能かわからない場合も、葬儀社に相談してみましょう。
無事、ご遺体の安置が完了したら、次は、葬儀社と葬儀の打ち合わせを行います。打ち合わせでは「葬儀日程」「斎場」「葬儀の形式」などを決めることになるため、自宅葬を希望している場合は、早めにお伝えしておくとよいでしょう。
納棺〜通夜振る舞い
葬儀の日時や内容が決まったら、お通夜の前に、故人のお身体を清めて死装束を着せ、棺に納める「納棺(のうかん)」を行います。納棺は、一般的にはお通夜の始まる3~4時間前に行われることが多いです。お通夜の後には、通夜振る舞いという会食の席が設けられますが、最近は、家族葬など簡略化された葬儀が増えていることもあり、会食を省略することも少なくありません。
葬儀・告別式〜精進落とし
お通夜の翌日の日中に葬儀・告別式が行われます。
告別式の後、棺を火葬場へと送り出す「出棺(しゅっかん)」が行われ、身内の方々は火葬場へと向かうことになります。火葬場では、火葬の後、お骨を骨壷に納める「収骨(しゅうこつ)」が行われ、精進落としという会食の席が設けられることが一般的です。
ちなみに、自宅葬の場合は、精進落としの会食も自宅で行うことが多くなっています。仕出しや出前を頼んだり、ご家族が手作りしたものを振る舞うこともあります。
自宅葬では、自宅の環境や駐車場の有無などの事前確認忘れずに(まとめ)
自宅葬を行う場合、まず、ご自宅が自宅葬を行える環境かどうかを確認する必要があります。
マンションの管理規約をチェックし、エレベーターや玄関などの搬入出経路に問題がないかも確認しましょう。その上で、参列者の駐車場の手配や、近隣住民へのご挨拶も忘れずに行うことが大切です。
また、自宅葬を行うにあたって、わからないことがあれば、葬儀社の事前相談もご活用ください。さがみ典礼では、24時間365日、いつでも無料の事前相談を承っています。また、事前相談で、葬儀費用が最大10.5万円引になる割引制度もございます。
まずは、ご相談だけでもお気軽にご連絡ください。
さがみ典礼の無料の事前相談はこちら
福島・岩手・山形・茨城・千葉での自宅葬は、さがみ典礼にお任せください

関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習にそって、皆様に気持ちよくお過ごしいただけるようなマナーを提供し、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。
今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下よりお電話でお問い合わせください。
TEL:0120-554-262
今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。
▼24時間365日、無料で電話相談受付中

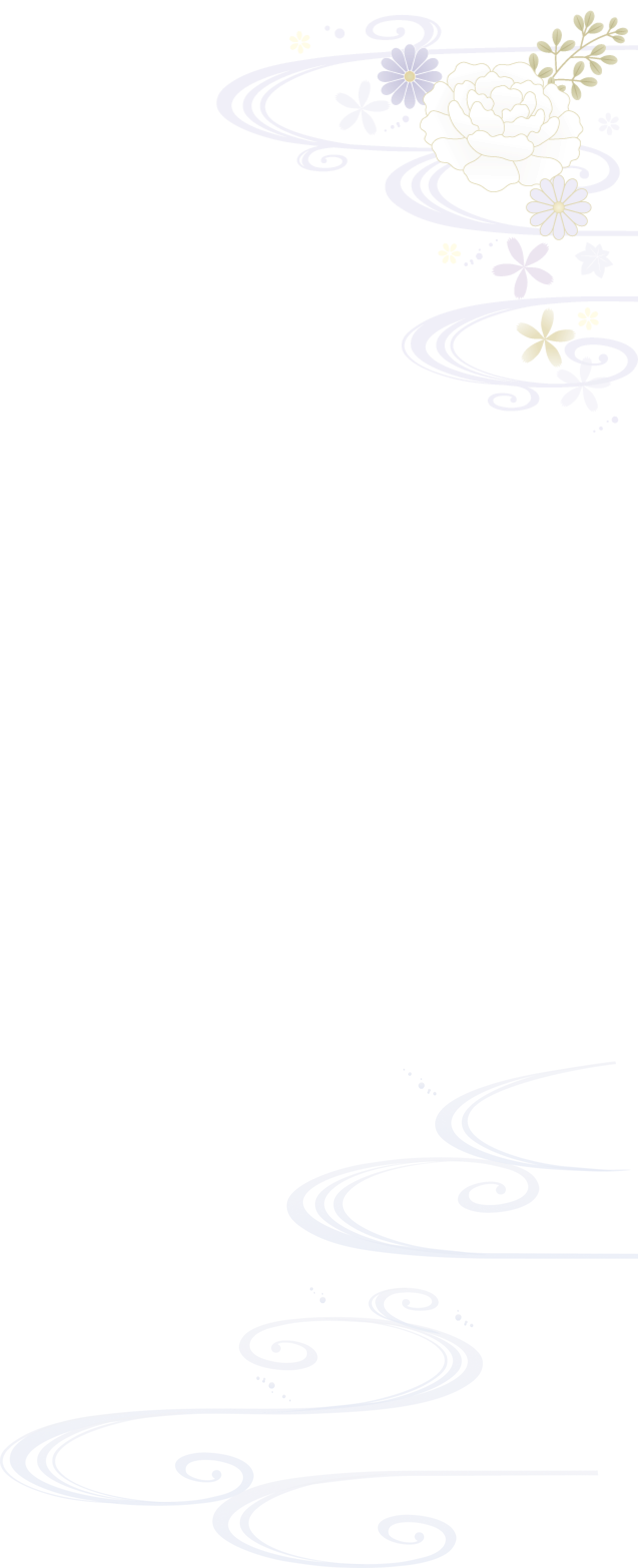
葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください
葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。
電話でお問い合わせ













