電話で
お問い合わせ
0120-554-262
葬儀の知識
火葬とは?必要な手続きや費用、火葬の流れを解説します
2025/7/14作成
2025/7/24更新

日本では、ほとんどのご遺体が火葬によって弔われます。しかし、火葬を行うためには、準備や手続きが必要です。 そこで今回は、火葬とはどんな弔い方なのかからはじまり、火葬を行うための手続きや火葬の流れ、費用などを解説します。 火葬場でのマナーや過ごし方、火葬にかかる所要時間にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
目 次
火葬とは?
火葬とは読んで字の通り、ご遺体を燃やして葬る弔い方法をいいます。
現代の日本は、ほぼ100%のご遺体が火葬によって弔われている「火葬大国」ですが、かつては土に埋葬して葬る「土葬」が一般的でした。
現在も一部の地域で土葬を行うことができますが、衛生面のリスクや土葬に適した広い土地の確保が難しいことなどから、火葬が主流となっています。
ちなみにイスラム教やキリスト教では、死後の復活を説く教義の影響から土葬が選ばれており、中東諸国やアメリカやフランス、イタリアなど、特にムスリムやカトリック教徒が多い国では、土葬が主流となっています。
火葬に必要な手続き
火葬を行うためには、以下の手続きが必要です。
・死亡診断書と死亡届の提出・火葬許可申請書の提出
・火葬場の予約
死亡診断書と死亡届の提出・火葬許可申請書の提出
火葬を行う際は「火葬許可証」が必要になります。
火葬許可証は、医師から発行される「死亡診断書」(または「死体検案書」)と「死亡届」を、住民票のある役所窓口に提出する際に、窓口に備え付けの「火葬許可申請書」に必要事項を記入して提出することで発行されます。
医師から発行される死亡診断書の左側が死亡届になっているので、そこに必要事項を記載した上で故人の住民票のある自治体窓口に持参しましょう。
火葬許可証はその場で発行されますので、火葬当日まで大切に保管し火葬場に持っていきます。火葬許可証がないと火葬ができないため、忘れないよう注意しましょう。
ちなみに、この手続きは葬儀社が代行してくれることも多いです。ご逝去後の慌ただしい中で、役所手続きを行うのは大変という場合は葬儀社に相談してみましょう。
火葬場の予約
火葬場の予約は、基本的には葬儀社が行います。
ご逝去後、所定の場所にご遺体を安置したのち、葬儀社との打ち合わせを行うことになりますが、打ち合わせで葬儀の日程を決める際に、ご遺族や僧侶のご都合と合わせて火葬場の空き状況も確認する必要があります。
火葬場の空き状況の確認や予約は、葬儀社だけが見ることができる斎場予約システムを通じて葬儀社が行うことが一般的です。個人予約を受け付けていない火葬場がほとんどのため、基本的には葬儀社にお願いしましょう。
福島・茨城・岩手・山形・千葉のご葬儀は、さがみ典礼にお任せください。
さがみ典礼に依頼する
死後24時間以内は火葬できないルールがある
日本には、墓地埋葬法という法律で「死後24時間は火葬することができない」というルールが定められています。
これは、まだ医療の発達していない昔に、仮死状態を死亡と誤認することがあり、亡くなった人が蘇生するケースが発生したため、蘇生の有無を確認する期間として設けられたものです。
医療が発達した現代では起こりにくいことではありますが、ご逝去後すぐに火葬をすることは、法律で禁じられていることを覚えておきましょう。
火葬の流れ
火葬は、以下の流れで執り行われます。
出棺
一般的なお葬式は、1日目にお通夜、2日目に葬儀・告別式・火葬と2日間かけて行われます。
葬儀会場で出棺の儀式が行われたのち、参列者に見送られながら故人の棺は火葬場へと出発します。
この時、火葬場に向かうのは、ご家族やご親族など親しい方のみとなり、一般参列者はここで解散となります。
喪主は霊柩車の助手席に乗って移動することが多いですが、それ以外の参列者の火葬場への移動は、人数に応じてマイクロバスなどを予約しておくと安心です。
納めの式
火葬場に着いたら、故人の棺を炉前にお運びし、僧侶の読経による「納めの式」が行われます。
納めの式では、喪主を筆頭に、故人と関係の近い人から順に焼香を行います。納めの式が終わったら、棺はいよいよ火葬炉の中へと運ばれ、火葬が執り行われます。
火葬時間は、ご遺体の体格や火葬炉の設備にもよりますが、大人の方で1時間〜2時間程度が目安となります。
お骨上げ(収骨・拾骨)
火葬が終わったら、火葬場のスタッフから火葬終了の案内があるので、指示に従って収骨室に集まります。収骨室では、火葬後のお骨を、参列者が二人一組になってお箸で拾い骨壷に収めていく「お骨上げ」を行います。
お骨上げでは、故人と血縁の深い人から順にペアになって、下半身から上半身に向けてお骨を拾っていきます。そして、最後に喉仏の骨を拾って終了となります。
お骨上げ終了後は、骨壷に収められたご遺骨がご遺族のお手元にかえってきます。
この時、火葬済みの押印がされた「火葬許可証」も受け取ることになりますが、それは、お墓に納骨する際に必要になるため、納骨まで大切に保管しておきましょう。
精進落とし
火葬後、参列者や僧侶をもてなす意味も込めて、精進落としという会食の席が設けられることが一般的です。
家族葬の場合は省略されることもありますが、その場合、僧侶には御膳料を、参列者にはお弁当などを用意してお渡しすることが一般的です。
精進落としは、故人の思い出を語り合い故人を偲ぶ場ですが、あまり長々とは行わず1〜2時間程度でお開きにするのがマナーです。
火葬を行う際に必要な費用はいくら?
火葬にかかる費用の内訳は、以下のとおりです。
火葬にかかる費用=火葬料+待合室利用料+骨壷代
火葬料
火葬料は、火葬そのものにかかる費用のことで、火葬場ごとに費用が定められています。
利用する火葬場が故人の住民票のある公営の火葬場であれば、市民割引が適用されるため無料〜1万円前後の費用で火葬を行うことができますが、市外の火葬場を利用したり、民営の火葬場を利用する場合は、それよりも割高な価格になります。
公営斎場の市民割引が適用される条件も、喪主が住民であれば割引対象になる場合があるなど、各自治体によって異なるため、お住まいの自治体の費用を確認しておきましょう。
待合室利用料
火葬は、およそ1時間〜2時間程度で終了しますが、火葬を行なっている間、参列者が待機する場所として、待合室を利用することができます。斎場にもよりますが、多くの場合有料となり、価格は斎場ごとに異なります。
骨壷代
火葬を終えたご遺骨を収めるための骨壷が必要になります。
こちらは、葬儀社のセット料金に含まれていることが多いですが、材質やデザインにこだわりたい場合は、追加料金が必要になります。
骨壷は、葬儀の打ち合わせの際に決めることになるため、希望があれば葬儀社に伝えるようにしましょう。
【公営の火葬場と民営の火葬場の違いと費用目安 】
●公営の火葬場
地方自治体によって運営されている火葬場です。
火葬料の目安 0円〜5万円程度
待合室利用料の目安 0円〜1万円程度
●民営の火葬場
民間企業によって運営されている火葬場です。
火葬料の目安 4万円〜10万円程度
待合室利用料の目安 2万円程度
火葬の際に心得ておきたいマナー
最後に、火葬場での服装や棺の中に入れる副葬品など、火葬に関わるマナーをご紹介します。
火葬場での服装マナー
火葬場での服装は、葬儀と同様に喪服を着用します。
男性なら光沢のない黒のスーツに白いワイシャツ、靴や靴下も黒で揃えて、派手な時計や結婚指輪以外のアクセサリーは外すのがマナーです。
女性は、光沢のない黒のスーツ/ワンピース/アンサンブルで、30デニール以下の黒いストッキングに黒のシンプルなパンプスを着用しましょう。
結婚指輪以外のアクセサリーは外すのがマナーですが、パールの一連のイヤリングやネックレスはよいとされています。二連のものは「不幸が重なる」と捉えられてしまうため避けるようにしましょう。
故人の棺に入れる副葬品のマナー
故人の棺に思い出の品などを副葬品として入れるケースがありますが、入れてよいものとよくないものがあるので注意しましょう。
基本的に、花や手紙などの可燃物は入れてもよいとされていますが、可燃物でも、分厚い本やスイカなどのフルーツ丸ごとなど、燃えるのに時間がかかるものはなるべく避けた方がよいでしょう。
また、金属製のアクセサリーやメガネなど燃え残ってしまうものや、革製品やビニール製品などのように燃えにくいもの、燃やすと有害物質を発生させてしまうものも避けるようにします。
よく、棺にお金を納めたいという人がいますが、お金を副葬品として入れることは法律に触れてしまう可能性があるので注意しましょう。三途の川の渡し賃として、納めたい場合は、紙にプリントされた六文銭を納めることが一般的です。
火葬の手続きや費用を知っておこう(まとめ)
現代の日本では、ほとんどのご遺体が火葬によって弔われています。そのため火葬に必要な手続きや費用は、事前に把握しておくと安心です。
火葬料は、どの火葬場を利用するかによって大きく変わりますが、故人の住民票のある自治体の公営の火葬場を利用するのが費用を抑えるポイントです。
火葬場の手続きや火葬場の予約など、火葬についてわからないことがあれば、葬儀社に相談するのもおすすめです。
さがみ典礼では、豊富な知識や経験に裏付けされたスタッフが、お客様のご葬儀へのご不安や疑問に寄り添えるよう、24時間365日無料でご相談を承っております。
まずは、お気軽にご相談ください。
福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください

関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。
今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。
TEL:0120-554-262
今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。
▼24時間365日、無料で電話相談受付中

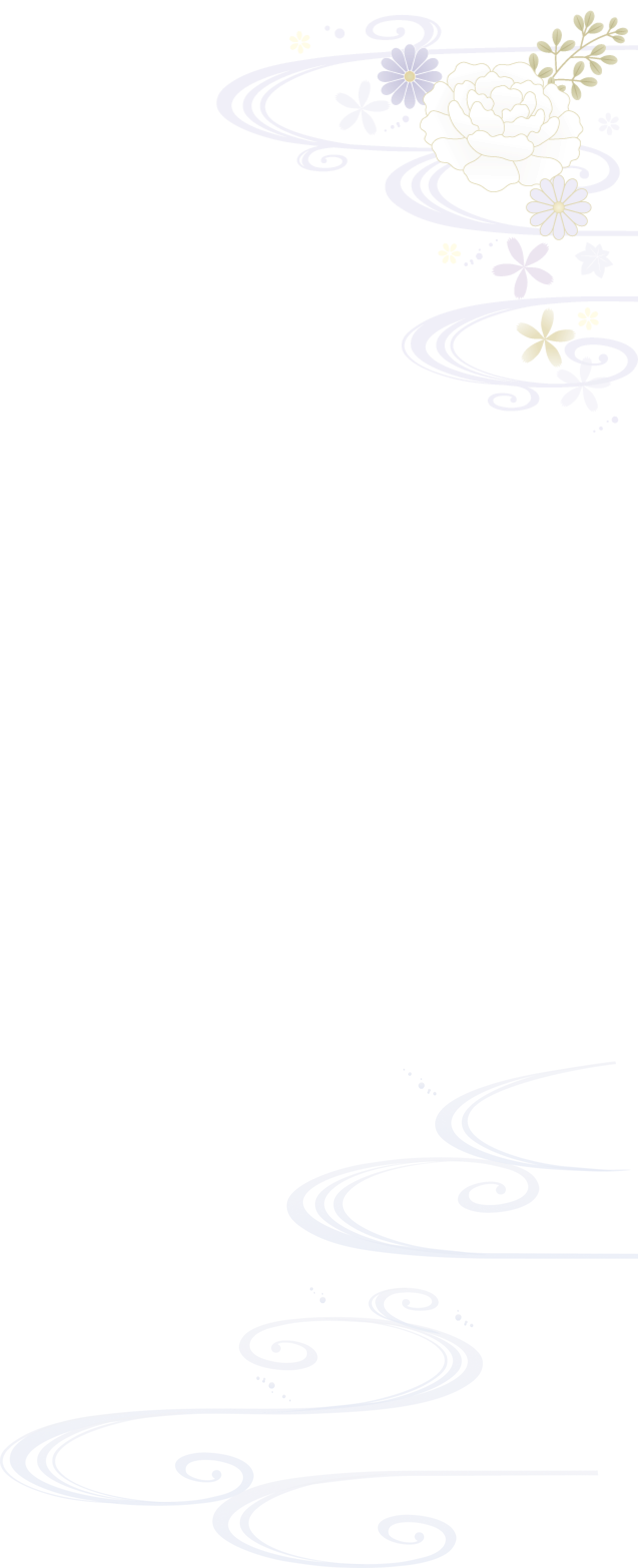
葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください
葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。
電話でお問い合わせ













