電話で
お問い合わせ
0120-554-262
葬儀の知識
葬儀社選びの5つのポイントー後悔のない葬儀にするためにー
2025/8/14作成
2025/8/20更新
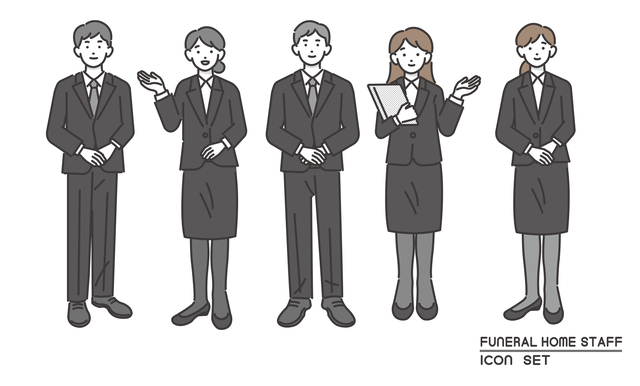
大切な方に万が一のことがあった時、ご家族が最初にすることは葬儀社の手配です。 なぜなら、病院やご自宅からご遺体を安全に搬送し、所定の場所に安置することは葬儀社の仕事だからです。 しかし、数ある葬儀社の中から自分にあった葬儀社を選ぶことは至難の業です。いざというときに迷わないためにも、失敗しない葬儀社の選び方を知っておくと安心です。 今回は、葬儀社を選ぶときのポイントをお伝えします。
目 次
葬儀社を手配するタイミングはお亡くなりになってすぐ
病院やご自宅等でお亡くなりになった場合、ご逝去後まもなく、医師から「死亡診断書」が発行されます。診断書を受け取ったら、次にすることが葬儀社の手配です。
葬儀社は、お通夜や葬儀・告別式を行うだけと思っている方も多いかもしれませんが、実は、お通夜までの間ご遺体を衛生的に保ったり、安全に搬送したり、所定の安置場所に安置したりすることも葬儀社の仕事の一つです。
また、身近な方を亡くされたご遺族は、知人への訃報連絡や死亡届の提出など多岐にわたる準備や手続きで慌ただしい時間を過ごすことになりますが、早めに葬儀社を手配しておくことで、一部の業務を代行してもらえたり、わからないことの相談にのってもらえたりと、葬儀社の存在がご遺族の安心材料や負担軽減につながります。
ただし、葬儀社選びは、ポイントを押さえて慎重に行いましょう。
葬儀社選びの5つのポイント
儀社選びでは、以下のポイントを押さえておきましょう。
スタッフの対応は問題ないか
葬儀社を選ぶ際は、窓口となるスタッフの対応をチェックすることも大切です。
葬儀社のスタッフとは、事前準備から火葬までの数日間、長い場合は数週間やり取りをすることになるため、信頼のおける担当者であることが重要です。
気持ちよくコミュニケーションが取れる相手であるかどうかはもちろんのこと「ご遺族の希望や要望を真摯に受けとめ、適切な提案をしてくれるか」「どんな些細な質問にもわかりやすく答えてくれるか」などを判断基準にするとよいでしょう。
なんでも気軽に相談でき、信頼関係を築ける担当者であれば、葬儀の間ご遺族の精神的なご負担も和らげてくれるでしょう。
希望を丁寧に聞いてくれるか
葬儀の内容に、故人やご遺族の希望がある場合、実現のために尽力してくれるかどうかも判断基準の一つです。
信頼に足る葬儀社であれば、お客様の希望を第一に考え、専門家として適切なプランを提案してくれるはずです。
中には、利益優先で不要なオプションやサービスを勧めてくる葬儀社もいるため注意が必要です。
経験豊富なスタッフがいるか
葬儀の企画・運営・進行を専門的に行うプロフェッショナルのことを「葬祭ディレクター」といいます。厚生労働省が認定する民間資格で、一級葬祭ディレクターになるには、学科試験と実技試験に加え5年以上の実務経験が必要になるなど、豊富な知識と経験が必要とされます。また、葬儀の知識だけでなく、落ち着きや忍耐力、誠実さなど人間的な資質も求められます。
葬儀社を選ぶ際には、一級葬祭ディレクターがたくさんいるかどうかを基準に選ぶというのも一つの方法です。
その地域での十分な実績があるか
葬儀社としての実績もポイントの一つです。葬儀は地域ごとの慣習が葬儀内容に影響する場合も多いため、地域の風習やしきたりに精通し、その地域で長年実績のある葬儀社を選ぶことも大切です。
また、ご遺体の搬送に関わる費用は距離によって追加料金が発生するため、亡くなられた場所に近い地域密着型の葬儀社に依頼する方が、費用を安く抑えられる可能性が高いです。
明確な見積書を提示してくれるか
見積書に細かい内訳まで記載されているかも確認しましょう。
項目ごとに金額が明記されていて、何にどれだけの費用がかかるかわかる見積書であれば問題ありませんが、一式〇〇円〜といったようにセット料金の表示のみであったり、細かい内訳が記載されていなかったりする場合は、後から追加料金を請求される可能性があるため注意が必要です。
誠実な葬儀社であれば、追加費用の可能性がある場合は、どのような条件で追加費用が発生するか、発生した場合いくらになるか、なども丁寧に説明をしてくれるはずです。
もし見積書に疑問点がある場合は、納得するまで質問しましょう。
葬儀社選びを始める前に決めておきたいこと
葬儀社選びを始める前に、費用・葬儀形式・葬儀場の場所や設備などは、あらかじめイメージを膨らませておきましょう。
また、葬儀に際しては故人の宗旨宗派の確認も必要です。
費用の上限を決めておく
どのくらいの金額までなら出せるという上限を決めておくと、その範囲内で何ができるかを相談することができるため、葬儀社との打ち合わせがスムーズに進みます。
どんなお葬式にしたいかをイメージしておく
葬儀には、一般葬・家族葬・一日葬・直葬などの種類があります。多くの関係者をお呼びして大々的に行う場合は一般葬、参列者を限定し身内だけでお見送りがしたい場合は家族葬というように、葬儀の規模や参列者の範囲などをイメージしておくとよいでしょう。
葬儀場の場所や必要な設備をイメージしておく
葬儀場は「自宅から近い方がいい」「親族などのアクセスを考えて駅チカがいい」「移動の手間を省くため火葬場と同じ敷地内にある施設がいい」など、葬儀会場の立地条件をイメージしておきましょう。
また、高齢者や乳幼児が参列される場合は「バリアフリーが充実している施設」など、設備についての希望もあらかじめイメージしておくとスムーズです。
故人の宗旨宗派を確認しておく
葬儀は、故人の宗旨宗派に基づいて執り行われます。
日本の多くの葬儀は仏教に基づく仏式ですが、神式やキリスト教式の宗教によって用意する祭壇などに違いがあります。
また、同じ仏式でも宗派ごとの違いもあるため、事前に故人の宗旨宗派を把握し、葬儀内容を決める打ち合わせの際に葬儀社に伝えられるようにしておきましょう。
失敗しない葬儀社選びにするために気を付けること
次に、失敗しない葬儀社選びのために気をつけることをお伝えします。
希望する葬儀を得意とする葬儀社に依頼する
最近は、葬儀社によって得意とする葬儀も異なる場合があります。
大きく分けて小規模な家族葬や一日葬などを得意とする葬儀社と、一般葬のような大規模な葬儀を得意とする葬儀社に分けられます。
そのため、もしあらかじめ希望の葬儀形式が決まっている場合は、希望する葬儀形式を得意とする葬儀社に依頼することをおすすめします。
見積もりは複数社に依頼し比較検討する
同じ葬儀内容でも、葬儀社によってセットに含まれる内容が異なるため最終的な金額が変わってくる場合が多いです。
また、見積書を依頼することで、葬儀社の対応もチェックすることができるため、葬儀の見積書は、複数社から取り寄せて、対応も含めて比較検討することをおすすめします。
また、依頼する際には、内訳まで含めた詳細な見積書をご提示いただくよう、お願いするとよいでしょう。
支払い期日や支払い方法も確認しておく
葬儀費用はまとまった金額が必要になるため、支払い期日や支払い方法を事前に把握しておくことも大切です。
ちなみに、一般的に支払い期日は葬儀後1週間から10日前後としている葬儀社が多くなっています。また決済方法は、現金・クレジットカード・葬儀ローンなどを選べる場合が多いです。ただし、葬儀社によっては、現金のみの可能性もあるため、希望する支払い方法に対応している葬儀社かどうかも事前に確認しておくと安心です。
契約をせかしてくる葬儀社は避ける
「今契約すれば割引になる」「早く決めないと予約が取れない可能性がある」など、契約をせかしてくる葬儀社は利益優先で不当な追加費用の請求をされる可能性が高いため気をつけましょう。
何よりもこちらの希望を優先して対応してくれる葬儀社を選ぶことが大切です。
葬儀社の事前相談を活用しよう
大切な方を亡くされ、精神的にも不安定な状況の中での葬儀社選びは、ご遺族にとって大きなご負担になってしまいます。
慌てて葬儀社を選んだために、「納得のいかない葬儀になってしまった」ということを避けるためにも、余裕のある時期に、できれば葬儀社の事前相談を活用し、複数の葬儀社を比較検討しておくことをおすすめします。
さがみ典礼では、豊富な知識や経験に裏付けされたスタッフが、お客様のご葬儀へのご不安や疑問に寄り添えるよう、24時間365日無料でご相談を承っております。
対面ではもちろん、お電話でもご相談いただけますので、お気軽にご連絡ください。
さがみ典礼の無料の事前相談はこちら
福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください
関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。
今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。
TEL:0120-554-262
今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。
▼24時間365日、無料で電話相談受付中

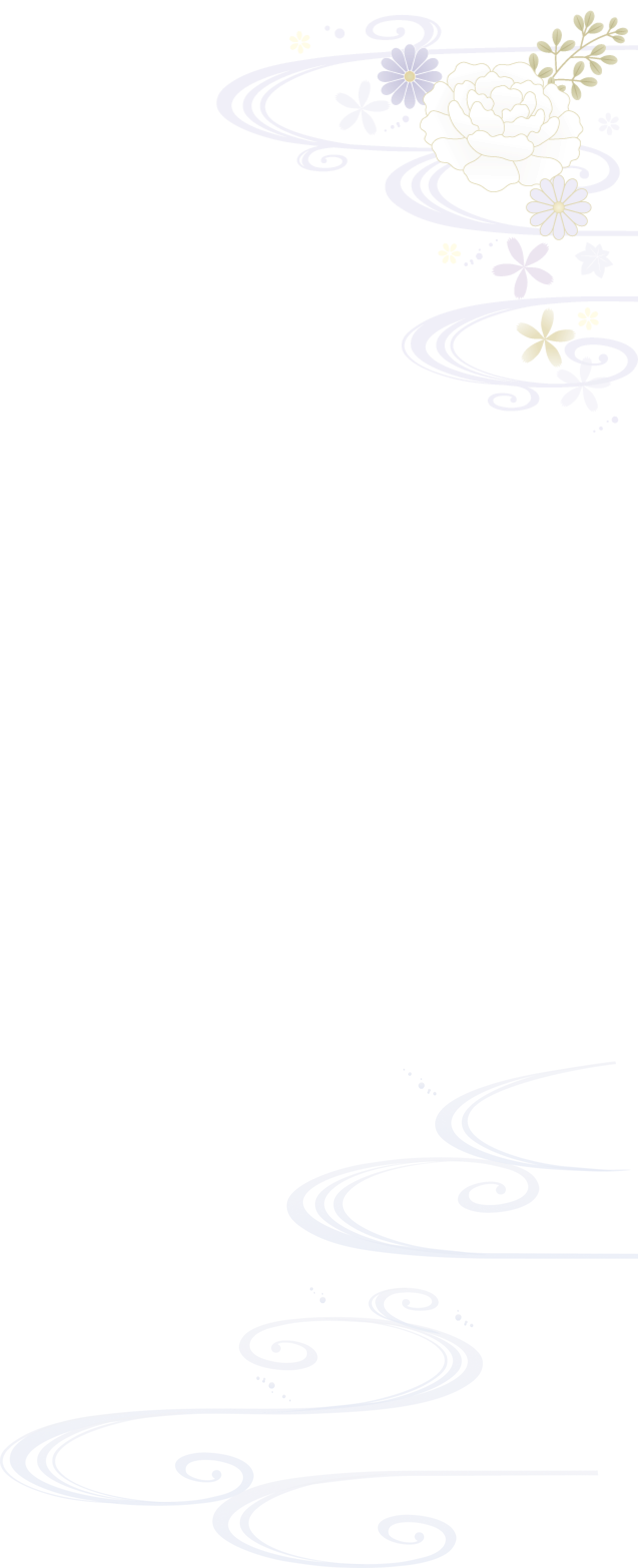
葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください
葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。
電話でお問い合わせ













